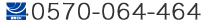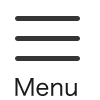大塚裕史の刑法通信

刑法コラム第102回
なぜ裁判例では制限故意説が有力なのか!?
刑法総論
2024.02.16
犯罪事実の認識はあるが、自己の行為が違法であるとは思わなかった場合を違法性の錯誤という。その取り扱いについては様々な見解があるが、近時の裁判例と通説は、責任主義の観点から違法性の意識の可能性がなければ犯罪は成立しないとしている。問題はその場合の法律構成である。この点、裁判例においては、違法性の意識の可能性を(責任)故意の要件と考える制限故意説が有力である。これによれば、違法性の意識の可能性がなければ故意が否定されることになる。これに対し、通説は、違法性の意識の可能性を(責任)故意とは別個の独立した責任要件と考える責任説を支持している。これによれば、違法性の意識の可能性がない場合は責任が阻却される。なぜなら、違法性の意識の可能性は故意犯だけでなく過失犯においても必要であるから、故意から切り離された独立した責任要件と考えるべきであるからである。たしかに、違法性の意識の可能性がない場合には過失犯の成立を認めるべきではないので、理論的には責任説が妥当である。それにもかかわらず、裁判例が責任説を採用しないのは、責任説によると、超法規的に責任を阻却することになるからである。裁判所は、構成要件に該当する行為の処罰を否定する場合にはきちんと明文根拠が必要であると考える。制限故意説は、38条1項の規定に基づき故意を否定することによって刑事責任を否定できる点でメリットがあるのである。
- 1/10(日)から配信開始!予備試験〈刑法〉全過去問から導く合格答案の道しるべ
- 2/7(土)開講!司法試験〈刑法〉全過去問から導く合格答案の道しるべ
記事一覧
- カテゴリーで探す
- 年度で探す
すべて表示
- 2026年1月6日 予備試験過去問検討の重要性
- 2025年11月27日 共同正犯の成立要件について
- 2025年10月20日 LEC『基本刑法』関連2講座の選び方!?
- 2024年12月20日 『基本刑法Ⅱ各論〔第4版〕』の出版に当たって
- 2024年12月13日 占有の有無の判断方法
- 2024年12月6日 不能犯の理解は規範論から
- 2024年11月22日 修正された客観的危険説は難しくない
- 2024年11月15日 刑法115条は受験生の盲点
- 2024年11月8日 予備試験受験生が司法試験の過去問を勉強する必要性
- 2024年11月1日 延焼可能性と機能的一体性を考慮するのはなぜか
- 2024年10月25日 まず包括一罪から検討せよ
- 2024年10月18日 自己名義のクレカの不正使用における盲点
- 2024年10月11日 「権利行使と恐喝」の論じ方
- 2024年10月4日 「恐喝」の論じ方
- 2024年9月27日 「占有の有無」をどの要件で論ずるのか・再論
- 2024年9月20日 旧司法試験過去問講座開講に当たって
- 2024年9月13日 抽象的事実の錯誤の論証例について・再論(その2)
- 2024年9月6日 抽象的事実の錯誤の論証例について・再論(その1)
- 2024年8月30日 抽象的事実の錯誤の論証例について
- 2024年8月23日 「実行行為」の説明法
- 2024年8月9日 『応用刑法』に関する誤解
- 2024年8月2日 共同正犯における正当防衛の成否
- 2024年7月26日 共同正犯における客観的帰責と主観的帰責
- 2024年7月19日 令和6年司法試験刑法の問題を見て
- 2024年7月12日 間接正犯の成立要件
- 2024年7月5日 故意があるのに故意がない
- 2024年6月28日 質疑応答③:横領行為の定義(その2)
- 2024年6月21日 質疑応答③:横領行為の定義(その1)
- 2024年6月14日 判例をどのように学ぶべきか
- 2024年6月7日 直前期における『刑法演習サブノート210問〔第2版〕』の使い方
- 2024年5月31日 参考人の虚偽の供述について供述録取書が作成された場合
- 2024年5月24日 参考人が虚偽の供述をしただけの場合
- 2024年5月17日 犯人「隠避」に当たるのは
- 2024年5月10日 「占有」の有無をどの要件で論ずるのか
- 2024年4月26日 新判例④:犯人による103条・104条の罪の教唆犯の成否
- 2024年4月19日 新判例③:業務上横領罪における身分
- 2024年4月12日 見解対立問題の傾向と対策
- 2024年4月5日 『応用刑法Ⅱ各論』の読み方
- 2024年3月29日 民法従属性と刑法的要保護性の関係
- 2024年3月22日 論証例スピードチェック講座開講に当たって
- 2024年3月15日 「民法従属性」がなぜ重要か
- 2024年3月1日 過剰防衛の場面での行為の一体性の要件
- 2024年2月23日 違法減少説と責任減少説の対立の意味は
- 2024年2月16日 なぜ裁判例では制限故意説が有力なのか
- 2024年2月9日 「誘発」と「異常性の低さ」がなぜ必要か
- 2024年2月2日 密接性と危険性の判断の仕方は
- 2024年1月26日 結合犯説に対する大いなる誤解
- 2024年1月19日 クロロホルム判例の正しい読み方
- 2024年1月8日 「公共の危険」に関する質疑応答
- 2023年12月18日 窃盗の後の暴行の3パターン
- 2023年12月11日 論点飛びつき症候群
- 2023年12月4日 刑事法ダブルA作戦
- 2023年11月27日 共謀の射程に関する質疑応答
- 2023年11月20日 「論点」が故意の問題に化けるとは
- 2023年11月13日 予備試験答案の特殊性
- 2023年11月6日 刑法答案の書き方
- 2023年10月30日 予備試験刑法の攻略法
- 2023年10月23日 他人のための事務か他人の事務か
- 2023年10月16日 図利加害目的の論じ方とは
- 2023年10月9日 実行共同正犯の論じ方とは
- 2023年10月2日 旧司法試験過去問を検討する意義とは
- 2023年9月25日 「強取した」といえるためには
- 2023年9月18日 水平的分業と信頼の原則
- 2023年9月4日 過失犯の共同正犯が成立するのは
- 2023年8月28日 予見可能性の考え方
- 2023年8月21日 過失の認定の仕方
- 2023年8月7日 危険の現実化説における条件関係の意義
- 2023年7月24日 故意の認定の仕方
- 2023年7月17日 性犯罪に関する刑法改正…強制から不同意へ
- 2023年7月10日 (構成要件的)故意と(責任)故意の関係
- 2023年7月3日 危険の現実化説における間接型の判断方法
- 2023年6月26日 新判例②:ユーチューバーの迷惑行為と窃盗罪
- 2023年6月19日 論点の本質論に遡るとは
- 2023年6月12日 作為可能性と作為容易性の関係は
- 2023年6月5日 延焼可能性と機能的一体性の関係は
- 2023年5月29日 新判例①:すり替え事案と窃盗罪の実行の着手
- 2023年5月22日 「共謀の射程」と「共同正犯関係の解消」の関係
- 2023年5月15日 中止犯の成立要件の論証について
- 2023年5月8日 中止犯における必要的減免の根拠
- 2023年4月24日 司法試験直前期の学習について
- 2023年4月3日 「入門刑法」の連載開始に当たって
- 2023年3月27日 厳格責任説と制限責任説の違いは何か
- 2023年3月20日 「人格の同一性」をどのように判断するか
- 2023年3月13日 「横領後の横領」では何を論ずればよいのか
- 2023年3月6日 不法領得の意思の発現行為といえるためには
- 2023年2月27日 単独正犯から書くか共同正犯から書くか
- 2023年2月20日 財産犯に関する論点の根底にあるもの
- 2023年2月13日 因果関係がないのに結果が帰責されることがあるか
- 2023年2月6日 治療用の管を抜くのは作為か不作為か
- 2023年1月30日 『応用刑法Ⅰ総論』の発刊にあたって
- 2023年1月23日 法益侵害と処罰根拠がイコールでない犯罪とは
- 2023年1月16日 「分かること」と「出来ること」は違う
- 2023年1月9日 旅券を不正に取得しても詐欺にはならないのは
- 2022年12月19日 「罪数論」は暗記科目ではない
- 2022年12月12日 令和4年度の「見解対立問題」の論じ方は
- 2022年12月5日 保護責任者遺棄罪と単純遺棄罪の関係は
- 2022年11月28日 「論点」の論じ方とは
- 2022年11月21日 「公共の危険」の認定における盲点とは
- 2022年11月14日 不法領得の意思の発現行為の「前提」とは
- 2022年11月7日 電子計算機使用詐欺罪に要注意
- 2022年10月31日 問題演習を怠ると
- 2022年10月24日 行為の一体性を説明すべき場合とは
- 2022年10月17日 正当防衛には2つの顔がある
- 2022年10月10日 侮辱罪の法定刑が変わると
- 2022年10月3日 予備試験刑法の口述試験対策
- 2022年9月26日 予備試の過去問と司試の過去問
- 2022年9月19日 「財産的損害」の有無がなぜ問題になるのか
- 2022年9月12日 「財産的損害」の有無をどこで論ずるのか
- 2022年9月5日 欺罔行為性の検討は何から始めるべきか
- 2022年8月29日 欺罔行為だけが詐欺罪の実行行為ではない
- 2022年8月22日 「共同正犯の処罰根拠」を正確に理解できているか
- 2022年8月8日 結果的加重犯の共同正犯の「肯否」と「成否」を区別できているか
- 2022年8月1日 結果的加重犯の共同正犯は頻出論点である
- 2022年7月25日 「強盗の機会」と因果関係
- 2022年7月18日 基本原理から考えるとは−未遂犯の処罰根拠を例に−
- 2022年7月11日 故意の認定の仕方
- 2022年7月4日 危険の現実化説をとると条件関係の判断は不要か
- 2022年6月27日 共謀共同正犯の規範定立の仕方
- 2022年6月20日 「ロースクール演習刑法」の使い方
- 2022年6月13日 「論点」の本質的理解の重要性
- 2022年6月6日 不可罰的事後行為と共罰的事後行為の相違
- 2022年5月30日 不作為犯の実行行為とは
- 2022年5月23日 作為との「同価値性」をどこに書くのか
- 2022年5月16日 不真正不作為犯の問題提起の仕方
- 2022年5月2日 学説対立問題の攻略法
- 2022年4月25日 刑法判例百選の学び方
- 2022年4月18日 不法領得の意思行為だけでは横領罪は成立しない
- 2022年4月11日 「2項強盗」を論ずる際に必要な「問題意識」とは
- 2022年4月4日 2項強盗における処分行為の要否は「論点」か
- 2022年3月28日 「占有侵害」の2つの意味
- 2022年3月21日 判例はいわゆる「占有説」ではない
- 2022年3月14日 不能犯と実行の着手はどのような関係があるのか
- 2022年3月7日 具体的危険説と危険の現実化説は両立するか
- 2022年2月28日 「実行行為」と「実行の着手」の関係
- 2022年2月21日 共犯問題では誰から先に書くか
- 2022年2月14日 相互利用・補充関係か因果性か
- 2022年2月7日 「間接正犯における正犯意思」
- 2022年1月31日 「不作為犯の実行行為とは」
- 2022年1月24日 「なぜ「学説対立問題」が出題されるようになったのか」
- 2022年1月17日 「過去問の検討をいつやるべきか」
- 2022年1月10日 「罪数論はなぜ重要か」
- 2021年12月27日 「『基本刑法Ⅱ各論』の使い方」
- 2021年12月19日 「合格答案に必要な条件とは」
- 2021年12月13日 「共同正犯の成立要件は」
- 2021年12月6日 「刑法の答案において「結論」の妥当性は要求されるか」