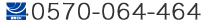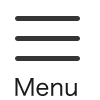予備試験の難易度と合格率、試験の傾向を分析しました
予備試験の試験制度・受験科目、法曹(弁護士・裁判官・検察官)になるまでの流れは理解できたところで、実際に予備試験を受験するにあたって気になるのは、試験の難易度や合格率ではないでしょうか。
年齢別、職種別、過去の司法試験の受験経験など、予備試験最終合格者のデータをもとに過去の予備試験の結果を振り返りました。
令和5年度 司法試験予備試験の結果
| 短答式試験 | 論文式試験 | 口述試験 | |
|---|---|---|---|
| 出願者 | 16,704人 | - | - |
| 受験者 | 13,372人 | 2,562 | 487 |
| 受験率 | 80.1% | 95.4% | 98.3% |
| 合格点 | 各科目の合計得点168点以上 (270点満点) |
245点以上 | 119点以上 |
| 合格者数 | 2,685人 | 487人 | 479人 |
| 平均点 | 183.4点 | 201.95点 | − |
令和5年司法試験予備試験をふりかえって
短答式試験
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 15,318人 | 14,317人 | 16,145人 | 16,704人 |
| 欠席者 | 4,710人 | 2,600人 | 3,141人 | 3,332人 |
| 受験者 | 10,608人 | 11,717人 | 13,004人 | 13,372人 |
| 採点対象者 | 10,550人 | 11,655人 | 12,882人 | 13,255人 |
| 合格点 (各科目の合計得点) |
156点以上 | 162点以上 | 159点以上 | 168点以上 |
| 合格者数 | 2,529人 | 2,723人 | 2,829人 | 2,685人 |
| 合格者の平均点 | 173.7点 | 178.7点 | 175.0点 | 183.4点 |
| 短答式試験合格率 | 23.9% | 23.2% | 21.7% | 20.3% |
論文式試験
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 2,439人 | 2,633人 | 2,695人 | 2,562人 |
| 採点対象者 | 2,428人 | 2,619人 | 2,679人 | 2,544人 |
| 合格点 | 230点以上 | 240点以上 | 255点以上 | 245点以上 |
| 合格者数 | 464人 | 479人 | 481人 | 487人 |
| 論文式試験合格率 | 19.1% | 18.2% | 17.9% | 19.1% |
| 対短答式試験受験者合格率 | 4.3% | 4.1% | 3.7% | 3.6% |
データから見る司法試験予備試験論文式試験
まず、最も注目の集まる合格者数についてですが、令和元年からの推移をみると、494人(令和元年)→464人(令和2年)→479人(令和3年)→481人(令和4年)となっており、450人以上500人未満の間に収まっていますが、今年もこの幅に収まる487人となり、例年どおりの水準といえるでしょう。
次に、合格率(採点対象者数に占める合格者数の割合)についてですが、これも令和元年からの推移をみると、約19.25%(令和元年)→約19.11%(令和2年)→約18.29%(令和3年)→約17.95%(令和4年)となっており、おおむね17%後半〜19%前半の割合に収まっていますが、今年もこの幅に収まる約19.14%となりました。司法試験短答式試験よりも科目数が多い予備試験短答式試験を突破した優秀な受験生であっても、予備試験論文式試験を突破できるのはおよそ5人に1人であり、非常に厳しい試験であることを物語っています。
なお、昨年(令和4年)から論文式試験の科目が変更されました(一般教養科目がなくなり、新たに選択科目が追加されました)。もっとも、合格者数や合格点にはさほど影響を与えていないものと思われます。
予備試験合格者数が500人を超えなかった理由について
これについては、①司法試験の受験資格を得るためのルートについては、あくまで法科大学院ルートがメインであって、予備試験ルートはバイパスにすぎないという位置付けを明確にすること、②予備試験合格者数を増加させてしまうと、法科大学院制度そのものが立ち行かなくなるため、法科大学院制度を守るためにも、予備試験合格者数を大幅に増加させるわけにはいかないこと、③司法試験の合格者数が約1,400〜1,700人で推移していることを踏まえると、予備試験の合格者数を大幅に増やすことはできないこと等が考えられます。
司法試験予備試験の論文式試験に合格するためには
論文式試験の合格率は、短答式試験を突破した受験生にとっては約17%後半〜19%前半と決して高いものではなく、難関試験ですが、〔設問〕の題意を正しく把握できる学力を身に付け、判例や条文の知識・制度趣旨に基づいた論理的な論述をすることができれば、必ず合格することができます。これは、司法試験予備試験の論文式試験に限らず、口述試験や、司法試験の論文式試験でも同じことがいえます。
司法試験予備試験は、平成23年から始まり、令和5年まで13年分の過去問の蓄積があります。したがって、まずはこの13年分の過去問をしっかりと分析し、実際に解いてみるところから始めましょう。
なお、一般教養科目の過去問を検討する必要はありませんが、選択科目の対策に当たっては、予備試験では昨年分しか蓄積がないことに加え、予備試験合格後も司法試験を受験することを踏まえると、司法試験の過去問を解くのが最も効率的だといえるでしょう。
また、具体的にどのような答案を作成すれば合格ラインに到達するのかという、いわば相場観を身に付けるためには、再現答案の分析が必要不可欠です。LECも予備試験受験生向けの再現答案集(『司法試験&予備試験 論文過去問 再現答案から出題趣旨を読み解く。』)を出版しておりますので、是非、これを活用して、合格答案の論述の流れを習得してください。
ゼロから始める方は、入門講座を活用して欲しいところです。また、予備試験論文式試験の答案練習会には是非とも参加し、答案を書いて、合格者に見てもらうことは必ず行うようにしましょう。本番さながらの実戦訓練を日頃から積み重ねることが試験対策上最も有意義であることは、誰もが認めるところです。
口述試験
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 462人 | 476人 | 481人 | 487人 |
| 合格点 | 119点以上 | 119点以上 | 119点以上 | 119点以上 |
| 合格者数 | 442人 | 467人 | 472人 | 479人 |
| 口述試験合格率 | 95.6% | 98.1% | 98.1% | 98.3% |
| 対短答式試験 受験者合格率 |
4.1% | 4.0% | 3.6% | 3.5% |
予備試験の口述試験に合格するためには
口述試験の受験者は、難関とされる予備試験短答式試験及び論文式試験の双方とも合格しています。そのため、口述試験の受験者のレベルは全体的に非常に高いといえますが、その中にあっても、口述試験に合格できない受験者は、約2〜5%程度存在します。
このことから、口述試験は、口述試験特有の対策を怠らなければほぼ確実に合格することができる試験である一方、口述試験特有の対策を講じることなく漫然と受験すれば不合格となるリスクが決して看過できない程度に存在する試験だと考えるべきです。
口述試験においても、出題された問題に対して解答するという形式に変わりはありません。しかし、口述試験の最も重要なポイントは、面接官(主査)と直接コミュニケーションを取りながら口頭で解答するという点です。短答式試験や論文式試験にはない独特の緊張感が受験者のメンタルに直接作用するため、うまくコミュニケーションを取ることができず、実力を発揮できないまま試験が終わってしまうという事態も起こり得ます(短答式試験や論文式試験であれば容易に解答できる内容であるにもかかわらず)。
そこで、口述試験を突破して最終合格を勝ち取るために最も効果的な対策は、実戦形式の対策、すなわち「口述模試」です。これを受けることで、実際の現場でも過度に緊張することなく、実力を発揮することが可能となるでしょう。
これから予備試験の最終合格を目指す方へ
最終合格者のうち、最も高い割合を占めているのは「大学在学中」の受験者です(最終合格者479人中、288人が「大学在学中」の受験者です)。このことからも分かるとおり、予備試験は、予備校の入門講座等を活用して効率的な勉強を行うことによって、大学在学中でも最終合格することが十分に可能な試験だということができます。また、司法試験の受験資格を一度喪失してしまったけれども、予備試験に最終合格して再度司法試験にチャレンジし、見事司法試験を突破される方も大勢いらっしゃいます。
予備試験に最終合格し、司法試験にも最終合格して法曹を目指すために最も重要なことの1つは、「できるだけ早い段階で効率的な学習を積み重ねること」です。
皆様が司法試験及び予備試験に合格なさることを心から祈念致します。