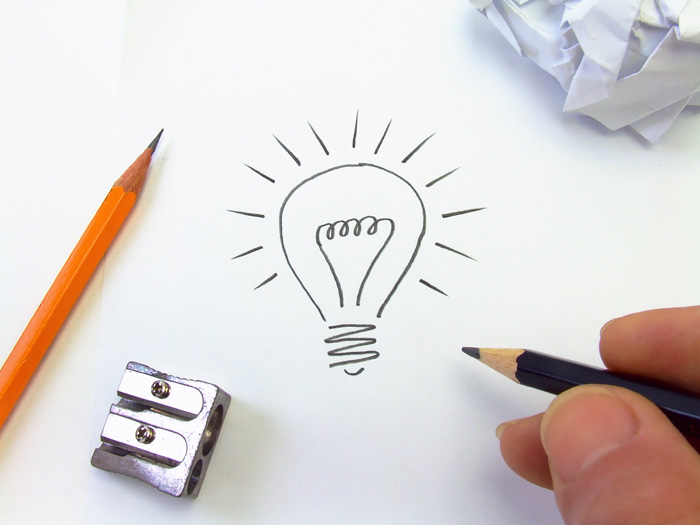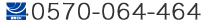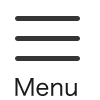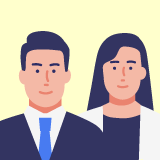�X�V���F2024�N7��5��
�������͑傫���킯�č��ƌ������E�n���������ɕ������܂��B
���ꂼ��ɁA�ǂ̂悤�Ȏd�����e�E�Ȃ���̈Ⴂ������̂����݂Ă����܂��傤�B
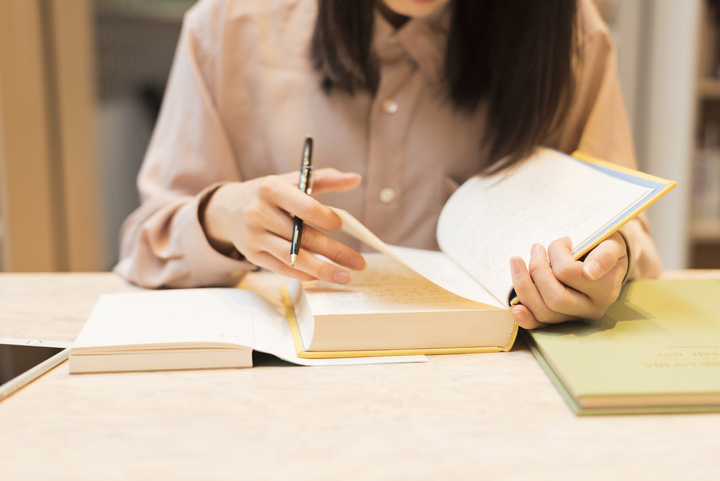
- �ڎ�
- �������́A���ƌ������ƒn���������ɕ��ނł���
- ���ƌ������ƒn���������̎d�����e�̈Ⴂ�́H
- ���ƌ������̎d��
- �n���������̎d��
- �������Ɍ����Ă���l
- ���ƌ������Ɍ����Ă���l
- �n���������Ɍ����Ă���l
- ���ƌ������E�n���������ւ̂Ȃ���̈Ⴂ
- �̗p�����T�v�ɂ���
- ���ƌ������̎����T�v
- �n���������̎����T�v
- ��y�̐�
- �܂Ƃ�
�������́A���ƌ������ƒn���������ɕ��ނł���
�������́A�傫�������āu���ƌ������v�Ɓu�n���������v�̂Q������A�̗p��E�d�����e�����ꂼ��قȂ�܂��B
���ƌ������̗̍p��́A���@�{�A�i�@�{�A�s���{�Ƃ��������{�̍������x���鍑�̋@�ւł��B����ɑ��A�n���������̗̍p��́A�̗p���ꂽ�n��ɖ��������s���T�[�r�X���s���n�������̂ł��B
���ꂼ��ɁA�ǂ̂悤�Ȏd���̈Ⴂ������̂����݂Ă����܂��傤�B
���ƌ������Ƃ́H
���ƌ������́A���S�̂�����ɓ��ꍑ�S�̂Ɋւ��Ɩ����s���������̂��Ƃ������܂��B��ɒ����Ȓ��Ƃ��̏o��@�ւɂ����ċƖ����s�Ȃ��܂��B��旧�ĂƋƖ����s���K�v�ƂȂ邽�߃X�P�[���̑傫���d������������܂��B�����Ȓ���O�ǁA����A�ٔ����Ȃǂ̍��Ƌ@�ւō��Ƃ̉^�c�Ɋ֘A�����Ɩ����s���X�y�V�����X�g�����ƌ������ł��B��\�I�ȋƖ��Ƃ��ẮA�������āA�@�����߂̐����A�\�Z�Ґ��A���ƁE�c��ւ̑Ή��A���v�����Ȃǂ��������܂��B
�n���������Ƃ́H
�n���������́A�s���{�����E�s�����E������ȂǂŒn��ɖ��������Ɩ����s�Ȃ��������̂��Ƃ������܂��B
�E���̋��^��\�Z�A�o���A��������p�n���Ȃǂ̑ΊO�I�ȋƖ��B���̑��ɂ��h�Б�A���ۑS�A�����̏[���A�����E�X�|�[�c�����̐��i�ȂǑ���ɂ킽�鑽�ʂȋƖ����s�Ȃ��܂��B
���ƌ������ƒn���������̎d�����e�̈Ⴂ�́H
���ƌ�����

�d�����e
- ���Ƒ����E
- ��ʂɃL�����A�Ƃ��钆���Ȓ��̊������ł��B����̊��E���āE�����A�@���̐������p�ȂNjɂ߂č��x�ȓ��e�ł���A�܂��ɍ��Ƃ�w�����Ă����ƌ������Ƃ��Ďd�������܂��B
- ���ƈ�ʐE
- �����E����ɒ����Ȓ��Ő���̊�旧�Ă�S������̂ɑ��A��ʐE�͍��i�����n���u���b�N�ɂ���e�Ȓ��̒n���x���ǂŐ���̎��{��S�����܂��B
����
�����ւ̒����Ȓ��̖{���ƑS���ÁX�Y�X�ɑ��݂��邱���Ȓ��̏o��@��
�n��������

�d�����e
- �s���{���E��
- �s���������\�Z�K�͂��傫�����߁A��K�͂Ȍ������Ƃ����{���܂��B�s���{�����͍��E���̑������́E��ƂȂǒc�̂�Ɏd�������邱�Ƃ���������܂��B
- �s�����E��E��
- �Z�������ɖ��������d���������Ȃ�܂��B
�Ⴆ�A�ːЁE�Z���[�Ɋւ���Ɩ��A�s�������H�E�����E�Βn�̕ی��Ǘ��A��ʔp����������T�C�N���A�З\�h�A�~�}�E�~�������Ȃǂ�������܂��B
�n���������͑傫�������ď����E�����E�㋉��3�ɂ킯�邱�Ƃ��ł��܂��B����͍̗p�����̓�Փx��\�����̂ň�ʓI�ɌĂ�Ă��܂��B�����̂ɂ���Ă͌Ăѕ����قȂ�܂��̂Ŏu�]�̎����̂��m�F���܂��傤�B
- �����c�������x���x����1�ԓ�Փx���Ⴂ�����ł��B�d�����e�͈�ʎ�������������悤�ł��B
- �����c�Z�呲���x���x���ł��B�����Ƃ܂Ƃ߂Ď��{����Ă��邱�Ƃ�����A�d���������Ɠ����Ɩ��Ɍg��邱�Ƃ�����܂��B
- �㋉�c�̗p���������呲���x���x���Ŏ����̂̊������Ƃ��č̗p����A���L���Ɩ��Ɍg���Ȃ��珸�i���邱�Ƃ��\�ł��B
����
�����̗p���ꂽ�����̖̂{����o��@��
- �_�܂��͂�������X�^�[�g�I�^
- �����𐿋�����
�������Ɍ����Ă���l
���ƌ������Ɍ����Ă���l
���ƌ������̂��������E�Ɍ����Ă���l�́A���̒������̂悤�ɕς��Ă��������A�Ƃ��������Ƃ��l���Ă���l�ł��B�����āA�����̔\�͂�����Ƃ������́A���Ԃ̌l���ƁA�n���������A���ƈ�ʐE�̊F����̔\�͂��ő�����������邱�Ƃ��ł���l�ł��B
���ƌ�������ڎw�������R

- ���Ƒ����E���i��
- ���ƌ������̋Ɩ��ɂ��āA��y����b���f���@�����A����ȍ~�A���g�̎�ō��̍����ł��鐭��̗��ĂɌg���A�����̐l����������Ŏd�����o���鍑�ƌ������̐E�Ƃɖ��͂������܂����B�����Ė��Ԋ�ƂŌg��邱�Ƃ�����A�v���W�F�N�g�̑傫����A����ǂ�����������Ȃǂ̕����Ɏ䂩��܂����B

- ���Ƒ����E���i��
- �Љ�̍L�͈͂ɂ킽�鏔���ɁA���Ɍ��݉����Ă���ƔۂƂ��킸�A���L���A�v���[�`���邱�Ƃ��ł���̂́A���ƌ������Ȃ�ł͂ƍl���ڎw���܂����B�����āA�ǂ̂悤�ȃo�b�N�O���E���h���������l�ł����Ă��u������O�v���������疾���ւƎ��R�ɑ����Ă�����Љ�ł��肽���ƍl��������ł��B

- ���ƈ�ʐE���i��
- ��s���ƒn���s�s����芪������ɑ傫�ȈႢ�����邱�Ƃ�F���������Ƃ���A�n���n���Ɍg��肽���Ƃ����v��������܂����B�������́A�ٓ��ɂ���đS���ʂ̃t�B�[���h�Ŋ��邱�Ƃ��ł���_�Ɠ��{�e�n�ɂ����č��コ��ɉߑa���Ə��q������i�W����Ȃ��ł������\�ȍs���T�[�r�X�̒����Ă��������Ƃ����v��������������u���悤�ɂȂ�܂����B
�n���������Ɍ����Ă���l
�n���������̂����s���{���̎d���Ɍ����Ă���l�́A���Ɗ�b�����́A��ƁA���Ԓc�̂Ȃǒ�����������A��b�����̂̐E���̊F���~���ɐ��s�ł���悤�C�z�肪�ł���l�ł��B����ɑ��āA�s�撬���̎d���Ɍ����Ă���l�́A���ڏZ���̊F����ɃT�[�r�X������̔����Ɋ�т����o�����Ƃ��ł���l�ł��B
�n����������ڎw�������R

- �n�����������i��
- �������͈�ʊ�ƂƈႢ�A���̒n��̏Z���܂��͍����S�̗̂��v��Nj����ē����̂ŁA�����ɃX�P�[���̑傫���ƑS�̗̂��Q�����̍����\�z����肪���̂���d�����낤�Ǝv���܂����B���ɁA�n���������͑S���o���̂Ȃ��悤�ȕ����ւƐ��N���ƂɈٓ��ƂȂ邽�ߗl�X�Ȍo����ςނ��Ƃ��ł��܂��B���̓������͍D��S�����Ȏ��g�̐��i�ƃ}�b�`���Ă���Ɗ����܂����B

- �n�����������i��
- ���́A�Љ���̉����ɍv���ł���d���Ƃ��Ďv�������̂��������ł����B���Ԋ�ƂƈقȂ�A���l�Ȏ�̂Ɍ����đ��p�I�ȕ��ʂ���A�v���[�`���邱�Ƃ��ł���Ƃ����_�ɖ��͂��������̂����������ł��B�܂��A�l�Ɛڂ��邱�Ƃ��D���Ȃ��߁A�n��̐l�X�̐g�߂ȑ��݂Ƃ��Ē��ڐ������Ƃ̂ł���n����������ڎw���܂����B
���ƌ������E�n���������ւ̂Ȃ���̈Ⴂ
���ƌ������ɂȂ邽�߂ɂ́A�l���@�����{���鍑�ƌ������̗p�����������i����K�v������܂��B
�呲���x�E�@���͍��Ƒ����E�A���ƈ�ʐE�A���Ɛ��E�i���Ő�劯�E������劯�E�J����ē����j�B�������x�͍��ƈ�ʐE�A���Ɛ��E�̎������s���Ă���A�敪��I�����Ď��܂��B
���ƈ�ʐE�i�呲���x�j�̏ꍇ�A�s���敪�i�n��̗p�j�E�y�؋敪�E���w�敪�E�_�w�敪�ȂǂƂ������敪���玩�g�̐��ɂ������敪��I�����܂��B
�n���������ɂȂ邽�߂ɂ́A�e�n�������̂����{����̗p�����������i����K�v������܂��B
�n�������������l�Ɏ��g�̐��ɂ������敪��I�������܂��B�܂��A�e�����̂��Ǝ��Ɏ������s���Ă��邽�ߎ������e����i���������̂ɂ���ĈقȂ�܂��B
�̗p�����T�v�ɂ���
���ƌ�����
���Ƒ����E�́A��N3�����{�ɑ�1�����������{����6����{�ɍŏI���i���\������܂��B���̌�6�����{��芯���K�₪�s�����X����l�����܂��B
��Ȏ������e�́A��1�������͕M�L�����Ŋ�b�\�͎����Ɛ�厎���i���ꎮ�j�����{����A��2�������Ő�厎���i�L�q���j�Ɩʐڎ������s��ꔻ�肳��܂��B���Ƒ����E�͉p�ꎎ���̓_���ɂ���ĉ��_����邽�߁ATOEIC�Ȃǂ̌�w�n�̑������邱�Ƃ��������߂��܂��B
���ɍ��ƈ�ʐE�͗�N6����{�ɑ�1�����������{����8�����{�ɍŏI���i���\������܂��B1���������i���\����ŏI���i�܂ł̊��ԂŊ����K�₪�s���邽�߁A�u�]���������ȂǑ��߂̏������K�v�ł��B
��Ȏ������e�́A��1�������͕M�L�����Ŋ�b�\�͎����Ɛ�厎���i���ꎮ�j�����{����A��2�������Ŗʐڎ������s��ꔻ�肳��܂��B
�n��������
�����ł́A�㋉�����i�呲���x�������j�ɂ��Đ������܂��B
��ɁA��1��������6�����{�ɑ�1�����������{����8���`9����{�ɂ����čŏI���i���\������܂��B
1���������e�́A���{�Ȗڎ����A���Ȗڎ��������{����邱�Ƃ��قƂ�ǂł��B�ŋ߂ł́A���ԏA�E�����Ŋ��p����Ă���A��b�\�͌����iSPI��SCOA�j�Ȃǂ����鎩���̂��o�Ă��Ă���A���l�����i��ł��܂��B
��ʓI�Ȍ����������̏ꍇ�A���{�����̓�Փx�͉Ȗڂ��Ƃɂ���ĈقȂ���̂́A�w�K�͈͂��L�����߁A��������Ƒ邱�Ƃ��K�v�ł��B��厎���ɂ��Ă��A�e�Ȗڂ��S���o�肳���Ƃ��������A�I�����̎����́A�ꕔ�̉Ȗڂ����w�肳��Ă��鎩���̂ȂǗl�X�ł��B
2�������͎�ɖʐڎ��������{����A�ʖʐڂ�W�c�ʐځA�W�c���_�Ƃ������l�X�Ȍ`�Ԃ̖ʐڎ������s��ꕡ������{���鎩���̂�����܂��B
��y�̐�

- ���� �痢����
�y��w���z��������w�i���s����w�j�݊w�����i
�y�ŏI���i��z���ƈ�ʐE�A���Ő�劯A�A�ٔ�����������ʐE�A�_�ˎs - �[�������ʐڑ�Ǝ�����T�|�[�g
�����w���u���⑼�̗\���Z�ł͂Ȃ�LEC��I���R�Ƃ��Ď��2����܂��B1�ڂ͏[�������ʐڑ�ł��B�����������͖ʐڑƂĂ��厖���ƕ����Ă������߁ALEC�̖c��ȏ��ʂƎ�����T�|�[�g�Ɏ䂩��܂����B���ʓI�Ƀ��A���ʐڃV�~�����[�V�����̐搶���ɂ͖ʐڑ�ŗl�X�Ȃ��Ƃ������Ă��������A�������g�ɑ傫�Ȏ��M�������Ƃ��ł��܂����B2�ڂ͎�����T�|�[�g�ł��B�u�t�̕��X�ƌ���2�`3��S�C���x�𗘗p�����Ă��������A���̑��k����Y�݂̑��k�܂ŕ��L�������Ă����������������ŕs���Ȃ������邱�Ƃ��ł��܂����B

- ��_ �^������
�y��w���z������w �݊w�����i
�y�ŏI���i��z���ƈ�ʐE�A���Ő�劯A�A���ʋ�T�� - ���ӉȖڂƋ��Ȗڂ̌���������
���̏ꍇ�A���Ȃ�ËL�Ȗڂɋ��ӎ�������A���w�n�̉ȖځA�@���n�̉Ȗڂ��D���ł����B���̂��߁A�I���ł���͈͂œ��ӉȖڂ�I�����邱�Ƃ͂������A���ӉȖځi���ɐ��I������~�N���E�}�N���j�͂W�`�X���̐������ɂł���悤�ɉ��x���J��Ԃ��ԈႦ���������������܂����B�@���ȖڂɊւ��Ă͍u�`�����x�������Ė@������ǂݎ��鐳�`�𗝉����悤�Ƃ��܂����B���ɋ��ȈËL�ȖڂɊւ��ẮA�������U����ڎw�������͖]�܂��A�����������ƂɎ��Ԃ��₷���Ƃ��A�e�L�X�g�����Ԃ��Đl�Ɩ��O���Ƃ肠�������ɒ@�����ނ��Ƃ��s���܂����B
�܂Ƃ�
���ƌ������A�n���������Ƃ��Ăł���d���͈قȂ�܂��B�����g���������ɂȂ������ɂǂ��������d���Ɍg����Ă��������̂��l���Ă݂܂��傤�B�ς��ƕ����Ȃ��ꍇ�͋����̂���Ȓ��⎩���̂̃z�[���y�[�W���݂Ă݂���A�J�Â���Ă���C�x���g�ɎQ�����Ă݂邱�Ƃ��I�X�X�����܂��B
�܂��A�u�]�悪���܂��Ă��Ȃ�����ǁA��������������n�߂Ă悢�̂��낤���H�Ǝ��₳��邱�Ƃ���������܂����A���m�ɂȂ��Ă��Ȃ��Ă��n�߂鎖���I�X�X�����܂��B�\���Z�ł͕���ł���J���L��������p�ӂ��Ă��邱�Ƃ��قƂ�ǂł����A���i�҂̑命������������n�߂Ă���ԂɎu�]������߂Ă��܂��B