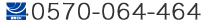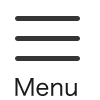�X�V���F2023�N12��28��

���Ƒ����E�Ƃ́A�����Ȓ��œ����A���ƌ������̊����E�����̂��Ƃ��w���܂��B�ȑO�́A�u�L�����A�����v�ƌĂ�Ă����̂ŁA���̕��������Ȃ��݂�����������邩������܂���B�Ɩ��̓n�[�h�ŁA�ӔC���d��ł����A�T�O�N��A�P�O�O�N��̓��{�̂���������肷��{��Ɏ��X�Ɗւ�邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����Ӗ��ł�肪�������ɑ傫�Ȏd���ł��B�����ł́A���ƌ����������E�̎d�����e�▣�́A�����̓�Փx������@�ɂ��ďЉ�܂��B
- �ڎ�
- ���Ƒ����E�̎d�����e�́H
- ���Ƒ����E�͐���̗��Ă��s��
- ���ƈ�ʐE�⍑�Ɛ��E�Ƃ̈Ⴂ
- �d�����e
- ����
- �N��
- ���i�E�L�����A
- ���Ƒ����E�ɂȂ�ɂ́H
- ���Ƒ����E�����ɍ��i���āA�����K��œ�������炤
- ���Ƒ����E�����̃X�P�W���[��
- �����敪���Ƃ̎����͈�
- ���Ƒ����E�����̓�Փx
- ���Ƒ����E�̖���
- ���܂߂Ȉٓ��ŁA�l�X�Ȍo����ς߂�
- ����w�ȂǃX�e�b�v�A�b�v�̓����p�ӂ���Ă���
- ���⍑���ɍv������X�P�[���̑傫�Ȏd�����ł���
- �o�ϓI�Ȉ���Ə[��������������
- ���Ƒ����E�ɂȂ邽�߂̏���
- ������
- �ʐڑ�
- �w�K��p�̑���
- ���Ƒ����E�������i�Ɗw���̊W��
- ���Ƒ����E�͂����H�J���ɂ���
- �c�Ǝ��Ԃ̒������N���[�Y�A�b�v����邱�Ƃ�
- �����������A�J�����̉��P�ւ̎��g�݂����i
- ���ꂼ��̏Ȓ��̃~�b�V�����̈Ⴂ
- ���Ƒ����E���� ���i�҂̐�
- �܂Ƃ�
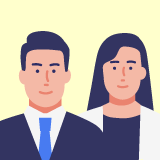
- �ďC�ҁFLEC���͔h�̍u�t�w
- LEC�͌����������̎w������30�N�ȏ�I
������������m��������v���ILEC�u�t�w���S���Ō�������ڎw�����̂��߂ɒ��J�Ɏw���B
�o���L�x�Ȏw���̃v�������̋^���Y�݁E�s�����������A�ŏI���i�E����܂ŁA���S�T�|�[�g���Ă����܂��B
���i�ɓ������͂̍u�t�w
- �_�܂��͂�������X�^�[�g�I�^
- �����𐿋�����
2025.26.27�N���i�ڕW
���Ƒ����E��R�[�X


- �z�_���̍�����厎���ɓ���

- �R���p�N�g�����{��

- �ʐڑ���}���c�[�}��
���Ƒ����E�̎d�����e�́H
���Ƒ����E�͐���̗��Ă��s��
���ƌ������̗̍p���������{����l���@�̋L�q�ɂ��A���Ƒ����E�����̎�|���u����̊��y�ї��Ė��͒����y�ь����Ɋւ��鎖�������̐E���Ƃ���W���̗̍p�����v�Ƃ���܂��B�@���͍ŏI�I�ɍ���̋c���ɂ���Đ������܂����A���̖@���Ă̑������쐬����̂͐��{�ł���A������哱����̂͊e�Ȓ��̐E���ł��B���Ƒ����E�͊e�Ȓ����S������Ɩ�����ɉ����āA���݂₱��܂ł̖���������A�C�O�ɂ�����ގ����x���r���������肵�A���{�̌���ɍ��킹������𗧈Ă��܂��B
�܂��A�@���̏̑f�Ă����̂����Ƒ����E�E���̖����Ȃ̂ŁA���x�ȕ��͂̍쐬�\�͂����߂��܂��B����ɁA�q��Ďx���ł���Ε����Ȋw�Ȃ�����J���Ȃ̗����Ɋւ��ȂǁA���Ȓ��Ƃ̒������K�v�ȋƖ�����������܂��̂ŁA���@�ւƂ̘A�g�E�����\�͂����x�Ȃ��̂����߂��܂��B
��ʂɍ��ƌ������͒n���������ɔ�ׂ�Ɓu�X�y�V�����X�g�v�Ƃ��Ĉ����܂����A���Ƒ����E�͏�������Ȓ��̋Ɩ��ɂ��Ă͕��L���S�����A�����v���s���Ă����Ӗ��ł́A�u�[�l�����X�g�v�ƌ����܂��B
���ƈ�ʐE�⍑�Ɛ��E�Ƃ̈Ⴂ
�d�����e
���ƈ�ʐE�̏ꍇ�A�����Ȓ��œ����ꍇ�ƁA�o��@�ւœ����ꍇ�ɕ�����܂����A�����Ȓ��œ����ꍇ�́A���Ƒ����E�̐E���ƂƂ��ɁA����̊��E���āE�����Ȃǂ��s���܂����A�����E�ȏ�Ɋe�������I�ɒS������X�������܂�܂��B�o��@�ւœ����ꍇ�́A�����Ȓ��ŗ��Ă��ꂽ�{����A�n��̎���ɉ����Ď��s������A�����Ƃ̑����ƂȂ��đΉ������肵�܂��B��̓I�ȋƖ����e�͏Ȓ��ɂ���ĈقȂ�܂��B
���Ɛ��E�́A���Ő�劯�������劯�A�J����ē��Ȃǂɕ�����܂����A���炩���߂ǂ������d�����s���̂������܂��Ă��܂��B�܂��A�Ɩ����e������啪��ɓ�������X���������Ȃ�܂��B
����
���Ƒ����E�̐E���͒����Ȓ��Ő���̊��E���Ă��s���̂ŁA�Ζ��n�̒��S�͓����ƂȂ�܂��B�������A�n���̎����c�����邽�߁A�o��@�ւ⎩���̂ɏo�����邱�Ƃ�����A�C�O�ɔh������邱�Ƃ������ł��B
����A���ƈ�ʐE�͊����ɂ���ĕς��܂����A�����Ȓ��Ζ��ł���ꍇ�͓����Ζ��ŏI�n���邱�Ƃ������A�o��@�Ζ��̏ꍇ�͓s���{���P�ʂ������̓u���b�N�P�ʁi�֓��n���A�ߋE�n���Ȃǁj�ł̋Ζ��ɂȂ邱�Ƃ������ł��B���Ɛ��E�̏ꍇ�����l�ŁA���Ő�劯�������劯�̓u���b�N�P�ʁA�J����ē��͓s���{���P�ʂ���{�ł��B
�N��
���t���[���t�l���ǂ̍��ƌ������̋��^�i�ߘa4�N�Łj�ɂ��A���Ƒ����E�i�呲���x�j�̏��C���͌��z��224,040�~�ł��i�{�{�Ȏ蓖���݁j�B�܂��A����Ƀ{�[�i�X��4.40�J���������̂ŁA�T��370���~�ł��B���ۂɂ́A����ɒʋΎ蓖��Z���蓖�Ȃǂ����Z����܂��B
���̌�A�N����d�ˁA���i����ɂ�ċ����͑������A�{�{�ȉے��⍲������35��719��2000�~�A�{�{�ȉے�������50��1260��1000�~�����f�����^��Ƃ��Ď�����Ă��܂��B
�ő��N���X�̊�Ƃ�O���n���͒Ⴂ���̂́A���Ԋ�ƑS�̂Ɣ�r����ƁA���Ȃ荂�����ɑ�����A�Ƃ����C���[�W�ł悢�ł��傤�B
���ƌ������̋��^�i���t���[�j ���Ƒ����E�̕��ϔN���͂ǂꂭ�炢�H
���i�E�L�����A
���i�̃y�[�X�͊����ɂ���Ď�قȂ�܂����A��ʐE�������|�I�ɑ����Ȃ�܂��B�ŏ��͌W������n�܂�͓̂����ł����A�W���ւ̏��i�͑����E�ł���S�`�T�N�ڂ���A��ʐE�ł���V�`�W�N�ڂɂȂ�܂��B�܂��A�ے��⍲�ւ̏��i�́A�����E�ł���V�`�X�N�A��ʐE�ł���P�V�`�Q�O�N���x������܂��B���ƌ������̏ꍇ�A�{�ȉے����ȏ�������ƌĂт܂����A��ʐE�Ŋ����ɏ��i����P�[�X�͏��Ȃ��ł��B�������A�����E�̏ꍇ�P�V�`�Q�O�N�ڈȍ~�ɉے����ȏ�ɏ��i���A���̌���\�͎���ŏ��i�̋@��傫���J���Ă��܂��B�ō���̎����������܂߁A�����E���͂��̑唼�������E�E���Ő�߂��܂��B
���Ƒ����E�ɂȂ�ɂ́H
���Ƒ����E�����ɍ��i���āA�����K��œ�������炤
���ƌ����������E�́A�t�����̏ꍇ�ł���A�P�������Ŋ�b�\�́i���{�j�A���̑��ꎎ�����s���܂��B�����āA�Q�������Ő����_�������i�@���҂͐���ۑ蓢�c�����j�A���L�q�����A�l���������s���A�ŏI���i�҂����肵�܂��B
�������A�ŏI���i��Ɋ����K����o�Ȃ�����Ƒ����E�̐E���ɂ͂Ȃ�܂���B���Ȍ�͊e�Ȓ��œ��{�̏�����S�������E�����Ƃ��Ċ��邱�ƂɂȂ�̂ŁA�����I�ȃr�W������L���Ă��邩�A�ӔC��w�����o��͂��邩�A�g�D�𑩂˂�҂Ƃ��ēK�Ȑl�����A��T�d�Ɍ��ɂ߂č̔ۂ����肵�܂��B���̃v���Z�X�������K��Ƃ����܂��B
�����K��̏ڍׂ̗���͊����ɂ���ĈقȂ�܂����A�l���S���҂�e�����̌���S���҂ƂP��łS�O�`�U�O�����x�̖ʐڂ��P���ɕ�����s���܂��B�I�l�̃v���Z�X�ł͏W�c���_�Ȃǂ����܂邱�Ƃ������ł��B�P���̊����K��ɗv���鎞�Ԃ͂P�Q���Ԉȏ�ɋy�Ԃ��Ƃ��������Ȃ��A������Œ�T���s���ē���҂����肵�܂��B
���肪�����銄���͍ŏI���i�ґS�̂�3�����x�ł���A��r�I���藦�������Ƃ���鋳�{�敪���i�҂ł��U���T�����x�Ƃ����A�Ō�ɂ��čő�֖̊�ł��B
���Ƒ����E�����̃X�P�W���[��
���ƌ����������E�i�呲���x�A���{�敪�ȊO�j�̗p�܂ł̃X�P�W���[��
2024�N�i�ߘa6�N�j�x�̗p�����@���{����
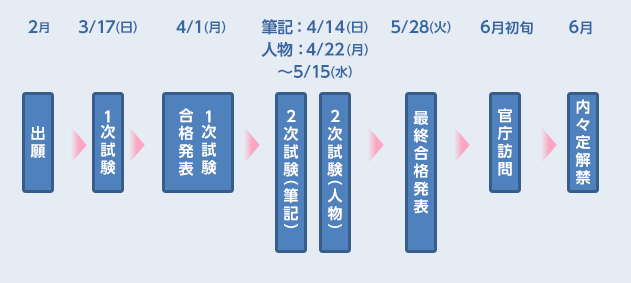
��2023�N������荑�Ƒ����E�����������O�|������܂��B ���ƌ������̗p�������x�������ɂ���
���ƌ����������E�i�呲���x�A���{�敪�j�̗p�܂ł̃X�P�W���[��
2023�N�i�ߘa5�N�j�x�̗p�����@���{����
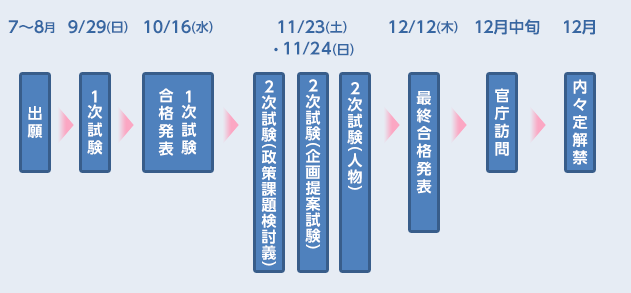
�����敪���Ƃ̎����͈�
�����E�i�@���敪�j
| �����Ȗ� | �������� | ���e | �z�_ | |
|---|---|---|---|---|
| �� 1 �� �� �� |
��b�\�͎��� �i�����I�����j |
2����20�� | 30�蒆30��� �m�\���� ���͗���⑩�A���f�E���I����⑭ �m������ ���R�E�l���E�Љ�Ɋւ��鎞���A���⑥ |
2/15 |
| ��厎�� �i�����I�����j |
3����30�� | 49�蒆40��� �m�K�{�Ȗځn ���@⑦�A�s���@⑫�A���@⑫ �m�I���Ȗځn�i18�蒆9��j ���@③�A�Y�@③�A�J���@③�A���ۖ@③�A�o�ϊw�E�����w⑥ |
3/15 | |
| �� 2 �� �� �� |
��厎�� �i�L�q���j |
3���� | 2�� 2�ȖڑI�� ���@�A�s���@�A���@�A���ۖ@�A��������② |
5/15 |
| �����_������ | 2���� | 1�� ����̊�旧�ĂɕK�v�Ȕ\�͂��̑������I�Ȕ��f�͋y�юv�l�͂ɂ��Ă̕M�L���� |
2/15 | |
| �l������ | �\ | �l���A�ΐl�I�\�͂Ȃǂɂ��Ă̌ʖʐ� | 3/15 | |
��2024�N�x��������b�\�͎����̏o�萔���������s���܂��B���ƌ������̗p�������x�������ɂ���
�����E�i�o�ϋ敪�j
| �����Ȗ� | �������� | ���e | �z�_ | |
|---|---|---|---|---|
| �� 1 �� �� �� |
��b�\�͎��� �i�����I�����j |
2����20�� | 30�蒆30��� �m�\���� ���͗���⑩�A���f�E���I����⑭ �m������ ���R�E�l���E�Љ�Ɋւ��鎞���A���⑥ |
2/15 |
| ��厎�� �i�����I�����j |
3����30�� | 46�蒆40��� �m�K�{�Ȗځn �o�ό��_⑯�A�����w�E�o�ϐ���⑤�A�o�ώ���⑤�A���v�w�E�v�ʌo�ϊw⑤ �m�I���Ȗځn�i15�蒆9��j �o�ώj�E�o�ώ���③�A���یo�ϊw③�A�o�c�w③�A���@③�A���@③ |
3/15 | |
| �� 2 �� �� �� |
��厎�� �i�L�q���j |
3���� | �K�{���1�ȖځA�I���Ȗ�2�Ȗ� �m�K�{�Ȗځn�@�o�ό��_ �m�I���Ȗځn �����w�A�o�ϐ���A��������② |
5/15 |
| �����_������ | 2���� | 1�� ����̊�旧�ĂɕK�v�Ȕ\�͂��̑������I�Ȕ��f�͋y�юv�l�͂ɂ��Ă̕M�L���� |
2/15 | |
| �l������ | �\ | �l���A�ΐl�I�\�͂Ȃǂɂ��Ă̌ʖʐ� | 3/15 | |
��2024�N�x��������b�\�͎����̏o�萔���������s���܂��B���ƌ������̗p�������x�������ɂ���
�����E�i�����E���ہE�l���敪�j
| �����Ȗ� | �������� | ���e | �z�_ | |
|---|---|---|---|---|
| �� 1 �� �� �� |
��b�\�͎��� �i�����I�����j |
2����20�� | 30�蒆30��� �m�\���� ���͗���⑩�A���f�E���I����⑭ �m������ ���R�E�l���E�Љ�Ɋւ��鎞���A���⑥ |
2/15 |
| ��厎�� �i�����I�����j |
3����30�� | 55�蒆40��� ���R�[�XA �����E���یn�� �m�K�{�Ȗځn �����w�I�A���ۊW�I�A���@�D �m�I���Ȗځn�i30��15��j �s���w�D�A���ێ���B�A���ۖ@�D�A�s���w�D�A���@�B�A�o�ϊw�B�A�����w�B�A�o�ϐ���B ���R�[�XB �l���n�� �m�K�{�Ȗځn �����w�E���ۊW�E���@�D�A�v�z�E�N�w�C�A���j�w�C�A���w�E�|�p�B�A�l���n���w�E�����l�ފw�A�A�S���w�@�A����w�B�A�Љ�w�B �m�I���Ȗځn�i30��15��j �v�z�E�N�w�E�A���j�w�E�A���w�E�|�p�E�A�l���n���w�E�����l�ފw�A�A�S���w�B�A����w�B�A�Љ�w�C |
3/15 | |
| �� 2 �� �� �� |
��厎�� �i�L�q���j |
3���� | 2�� ���R�[�XA �����E���یn�� �ȉ����2�ȖڑI�� �����w�A�s���w�A���@�A���ۊW�A�A���ۖ@�A��������A ���R�[�XB �l���n�� �ȉ����1�Ȗڂ܂���2�ȖڑI�� �v�z�E�N�w�A�A���j�w�A�A���|�E�|�p�A |
5/15 |
| �����_������ | 2���� | 1�� ����̊�旧�ĂɕK�v�Ȕ\�͂��̑������I�Ȕ��f�͋y�юv�l�͂ɂ��Ă̕M�L���� |
2/15 | |
| �l������ | �\ | �l���A�ΐl�I�\�͂Ȃǂɂ��Ă̌ʖʐ� | 3/15 | |
��2024�N�x��������b�\�͎����̏o�萔���������s���܂��B���ƌ������̗p�������x�������ɂ���
�����E�i���{�敪�j
| �����Ȗ� | �������� | ���e | �z�_ | |
|---|---|---|---|---|
| �� 1 �� �� �� |
��b�\�͎��� �i�����I�����j |
Ⅰ���F2���� | Ⅰ���F�m�\���� ���͗���⑧�A���f�E���I����⑯ |
Ⅰ���F3/28 |
| Ⅱ���F1����30�� | Ⅱ���F�m������ ���R⑩�A�l��⑩�A�Љ�⑩ |
Ⅱ���F2/28 | ||
| �����_������ | 4���� | Ⅰ�F����̊�旧�Ă̊�b�ƂȂ鋳�{�E�N�w�I�ȍl�����Ɋւ������ Ⅱ�F��̓I�Ȑ���ۑ�Ɋւ������ |
8/28 | |
| �� 2 �� �� �� |
�����_������ | Ⅰ���F1����30�� | Ⅰ���F����T�v�����i�v���[���e�[�V�����V�[�g�쐬�j | 5/28 |
| Ⅱ���F1���Ԓ��x | Ⅱ���F�v���[���e�[�V�����y�ю��^���� | |||
| ����ۑ蓢�_���� | 1���Ԕ����x | �\ | 4/28 | |
| �l������ | �\ | �l���A�ΐl�I�\�͂Ȃǂɂ��Ă̌ʖʐ� | 6/28 | |
��2024�N�x��������b�\�͎����̏o�萔���������s���܂��B���ƌ������̗p�������x�������ɂ���
���Ƒ����E�����̓�Փx
���Ƒ����E�́A����x�̕M�L�����E�ʐڎ����ɉ����A�e�����Ȓ��̗̍p�ʐځi�����K��j�����蔲���Ȃ���Ȃ�Ȃ��L���̓�֎����ł��B�ŏI���i�܂ł̔{���͉ߋ�4�N�Ԃŕ���16.6�{�Ƌ������̍��������ƂȂ��Ă��܂��B���ƈ�ʐE�̋������Ɣ�r���Ă��A���ɍ����������ł��邱�Ƃ�������܂��B�ߔN�ł͓�����w�E���s��w�Ƃ�����������w�ȊO�ɂ�����c��w�E�c���`�m��w�E�����ّ�w�E������w�Ƃ���������o�g�҂̗̍p�������Ă��Ă��܂��B
①���Ƒ����E�i�呲���x�j�@���敪
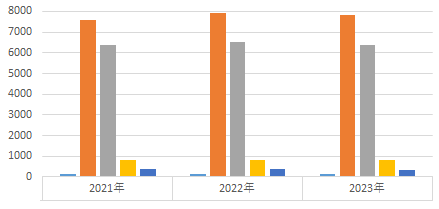
| 2021�N | 2022�N | 2023�N | |
|---|---|---|---|
| ■�̗p�\�萔 | 145 | 135 | 125 |
| ■�\���Ґ� | 7,601 | 7,945 | 7,834 |
| ■�Ґ� | 6,383 | 6,511 | 6,363 |
| ■1���������i | 829 | 796 | 825 |
| ■�ŏI���i | 406 | 380 | 352 |
| �{�� | 15.7 | 17.1 | 18.1 |
②���ƈ�ʐE�i�呲���x�j�s���i�֓��b�M�z�j
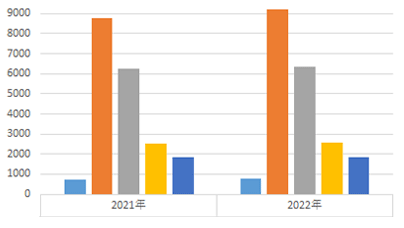
| 2021�N | 2022�N | |
|---|---|---|
| ■�̗p�\�萔 | 730 | 780 |
| ■�\���Ґ� | 8,753 | 9,204 |
| ■�Ґ� | 6,258 | 6,357 |
| ■1���������i | 2,531 | 2,565 |
| ■�ŏI���i | 1,825 | 1,844 |
| �{�� | 3.4 | 3.4 |
���ڍׂ��u���ƌ��������� �̗p���NAVI�v�����m�F���������B
���Ƒ����E�̖���
���܂߂Ȉٓ��ŁA�l�X�Ȍo����ς߂�
���Ƒ����E�̏ꍇ�A��ʐE�ɔ�ׂ��ٓ��̃y�[�X�����ɑ������Ƃ������I�ł��B�����̌������̏ꍇ�A�R�`�T�N��P�ʂƂ��ĕ����ړ����s���A�o����ςݏd�˂Ă����܂����A���Ƒ����E�̏ꍇ�́A�Z���Ԃ̂����ɁA�l�X�ȕ������o�����邱�Ƃŕ��L�����������A�R�O��O������͉ے��⍲���Ƃ��Ă�����x�����𑩂˂闧��ւƐ������܂��B�ٓ��̃y�[�X�͒����Ă��Q�N���x�A�Z���ƂP�N�����ł���A���Ȍ�P�O�N�ԂłP�O�����ȏ�̕������o������P�[�X������܂��B
����w�ȂǃX�e�b�v�A�b�v�̓����p�ӂ���Ă���
��w�͂̌���⍑�ۓI�Ȓm���̊l���A��含���K�����邽�߂ɁA���Ƒ����E�E���ɂ��������̊C�O�o����ςދ@��^�����Ă��܂��B�����́A�l���@�̒����݊O���������x�Ȃǂ𗘗p���čs���A���O���̑�w�@�i�C�m�ے����͔��m�ے��j�ɔh������A�����ɏ]�����邱�ƂɂȂ�܂��B�������e�͊����ɂ���ĈقȂ�A�����Ȋw�ȂȂ�F���W�⌴�q�͊W�A�_�ѐ��Y�ȂȂ������ȂǂƂȂ�܂��B�����̗��w��p�͍���ɂ���Ęd���A�A����ɂ������荂�x�Ȑ���̊�旧�ĂɊ�������܂��B
���⍑���ɍv������X�P�[���̑傫�Ȏd�����ł���

�u�����\���v�Ƃ������t���l�X�ȏ�ʂŎ��グ���钆�A�n�悾���łȂ��A���{�S�̂̎����\�����l���Ȃ��琧�x�v���s���̂����Ƒ����E�̖����ł��B�e�Ȓ������s���鑍���E�̐E���Љ�p���t���b�g�����Ă��A�u���悢�Љ�Â���ɍv���v�u�g�g�݂��\�z�v�Ȃǂ̌��t����肪����ʔ����Ƃ��ċ������܂��B���̐��Љ�S�̂⍑�ƁA���ɂ͐��E�ɉe����^���邱�Ƃɂ��Ȃ�A���ꂾ���X�P�[���̑傫�Ȏd���Ɍg���閯�Ԋ�Ƃ͂܂��Ȃ��ƌ����Ă��悢�ł��傤�B
�o�ϓI�Ȉ���Ə[��������������
���Ƒ����E�̋������f���\�ɂ��A35�̉ے��⍲����730���~���x�Ƃ����̂͏Љ�܂����B��������z�̋��^�Ɋ��Z����Ɩ�44���~�ł��B����A�����J���Ȃ̒����\����{���v�����ɂ��ƁA���Ƃ�30�`34��35�`39�̕��ϒl����32���~�ł���A4���قǍ������Ƃ��킩��܂��B
�܂��A���Ԋ�Ƃɔ�ׂČ������͑S�̂Ƃ��āA�Z���蓖�A�ʋΎ蓖�A�}�{�蓖�ȂǁA�e��蓖���[�����Ă���A�玙�x�Ɛ��x����x�Ɛ��x�̎擾���ϋɓI�ɍs���Ă��܂��B
�܂��A���ƌ������́u���ƌ��������ϑg���v�ɉ������A���̑g���������p�ł���{�݂��S���e�n�ɑ��݂��邽�߁A�[�����������������邱�Ƃ��ł��܂��B
���Ƒ����E�ɂȂ邽�߂̏���
������
���i���邽�߂̕��@�́H
��b�\�͎����ł͐��I�����ƕ��͗����őS�̂̂R���̂Q�̔z�_���߂܂��B���ɁA�p�ꂪ�V��Ƒ��̎����ɔ�ׂđ����̂ŁA�p��͂̋����͕s���ł��B�܂��A���I�����͑S�̂̂S�����߂�̂ŁA��b�\�͎����ł̍ŗD��Ȗڂł��B���Ȗ��͎敪�̑I�����挈�ł��B�����n�̋敪�ł͐������ہA�@���A�o�ς̂R������A�ł��̗p���������͖̂@���ł����A�������ۂ̗̍p���������X���ɂ���܂��B�@���Ȃ�Ό��@�A���@�A�s���@�őS�̂̂قڂW�����A�������ۋ敪�ł���ΐ����w�A���ۊW�A���@�őS�̂̂U�����߂�̂ŁA�����̉Ȗڂ���D�悵�Ċw�K���܂��傤�B
���ꎎ���̍��i�ɕK�v�ȃ{�[�_�[���C���́A�@���敪�̏ꍇ�T���T���`�U�����x�A�������ۋ敪�͂T���`�T���T�����x�ł��B

����������J�n��������H
�����������̊w�K���Ԃ͈�ʓI�ɊT�˂P�N�ƌ����܂��B���Ƒ����E�̎����͖��N�S���ɍs����̂ŁA�w�����ł���R�t�A�@���ł���ΏC�m�P�N�Ȃ̂ŁA�@���Ҏ�������ꍇ�́A��w�@���w�Ɠ����Ɏ���������邱�ƂɂȂ�܂��B
�������A���Ƒ����E�́A���ƈ�ʐE��n���㋉�����w�K����Ȗڐ��͏��Ȃ��̂ŁA�Ă��납��n�߂������萔���܂��B����A�����K��ɂ����ĕ�����T�[�N���A�A���o�C�g�̂ق��A�w�Ƃ�C�O�̌o���Ȃǂ��A�s�[���ޗ��Ƃ��邽�߁A�Q�ȂǑ������珀�����J�n���A�����̊����Ɠ������s�ŏ�����������Ă������������ł��B
�ʐڑ�
���Ƒ����E�̓����������邽�߂ɂ́A�Q�������Ƃ��čs����l���@�ʐڂ����łȂ��A�����K��̑������܂����B������T�[�N���A�A���o�C�g�͂������̂��ƁA�w�Ƃɂ��͂����邱�Ƃ����߂��܂��B�܂��A���ۓI���������Ă���l�ނ��d�������̂ŁA���w�ȂNJC�O�o�����A�s�[���ޗ��Ɏg�����������ł��B�����̊����̊J�n�����́A��w�P�̏t�ȂǁA������Α����قǂ悢�A�Ƃ����܂��B��w�Q�A�R����l���n�߂����́A���s���Ă��銈�����ő���撣��܂��傤�B���ۓI����̓j���[�X��V������������܂��B
����A�����K���ɒ������鏀���Ƃ��ẮA��N�A�����O�N�̓~����t�ɂ����āA����u�����e�Ȓ��̗̍p�S���҂Ƃ̖ʒk�Ȃǂ̃C�x���g�������s���܂��B�����ɐ������Q�����A�e�Ȓ��̐�������Ɋւ�����ӎ���|�����Ƃ��A�����K��ŋ��߂��鎩���Ȃ�̍��Ƒ���`�����ƂɂȂ���܂��B
�����K��͂P�ڂ̊����ɖK�₷��ƁA�Q���ԋ�Ƃ������[�������邽�߁A�ŏ��͂R�̊����ɖK�₷�邱�Ƃ��ł��܂��B�����̕���̎d���͐F�X�ȃp�^�[��������̂ŁA�ǂ��������ʂ��獑�Ƃɍv���������̂��A�����̊S����ɂ�����炸�A������L�������Ƃ��K�v�ł��B
�w�K��p�̑���
���Ƒ����E�̑�u���͂������̗\���Z�ŗp�ӂ���Ă���A�T�O�`�U�O�����x������ł��B��{�I�ɂ́A���̋��z�ōu�`�����łȂ��A�e�L�X�g�A�ߋ����W���̑�����܂܂�Ă���A�w�K�ɂ����鑊�k��ʐڑ�Ȃǂ��܂܂�Ă���̂���ʓI�ł��B
�������A�\���Z�ɂ���ē��ɗ͂����Ă��镔�����ǂ����͈Ⴂ������A�M�L�����ō����_����邱�Ƃ��ŗD��Ƃ���Ƃ���A���k��ʐڂȂǂ̐l�I�t�H���[�ɗ͂����Ă���Ƃ���A�Ζʂł̎��Ƃ���̂Ƃ���Ƃ���ȂǁA���F������܂��B�������g�̋��Z�n��w�͐����A�\���Z�̕��͋C�Ȃǂ��m�F���A�w�K����ꏊ��I��ł����Ƃ悢�ł��傤�B
���݂̍��Ƒ����E�́A�ȑO�Ɣ�ׂ�Ƌ����������ቺ���Ă���A���ꎎ���̃{�[�_�[���C�����ቺ�X���ɂ���܂��B����A�����K��ɂ��i�荞�݂͈ˑR�Ƃ��Č������̂ŁA�u�����������͏A�E�����ł���v�Ƃ������Ƃ�O���ɂ������������s�����Ƃ��A��]�����ւ̓���Ɍ��ѕt���₷���Ȃ�܂��B
���Ƒ����E�������i�Ɗw���̊W��
���Ƒ����E�����ł́A�u�ŏI���i�v���S�[���ł͂���܂���B�u�ŏI���i�v�́A�����܂ł����ƌ����������E�̗p�����̑�2�������ɍ��i�������Ƃ��Ӗ����A���̒i�K�Ƃ��Ċ�]����Ȓ���K�₷��u�����K��v��A���ꂼ��̏Ȓ�����A�E����������u����ʒm�v�����K�v������܂��B
�l���@���u�����E�����i�@���Ҏ����E�呲���x�����j�o�g��w�ʍ��i�҈ꗗ�v�����\����Ă��܂��B ���Ƒ����E�����̍ŏI���i�҂ɂ́A�ǂ̂悤�ȑ�w�o�g�҂������̂��݂Ă݂܂��傤�B
| ���� | ��w�� | ���i�Ґ� |
|---|---|---|
| 1 | ������w | 193 |
| 2 | ���s��w | 118 |
| 3 | �k�C����w | 97 |
| 4 | ����c��w | 96 |
| 5 | �����ّ�w | 78 |
| 6 | ���k��w | 70 |
| 7 | ������w | 68 |
| 8 | ���R��w | 55 |
| 9 | ��B��w | 51 |
| 10 | �c���`�m��w | 51 |
| 11 | �L����w | 50 |
| 12 | ������w | 49 |
| 12 | ����w | 48 |
| 14 | ��t��w | 47 |
| 15 | �����H�Ƒ�w | 46 |
| 16 | �}�g��w | 41 |
| 17 | �������ȑ�w | 40 |
| 18 | ��������w | 37 |
| 19 | �V����w | 35 |
| 19 | ������w | 35 |
��̕\�̂Ƃ���A���i�Ґ���ʍZ�ɍ�����w����������܂����A������w����ʂɈʒu���Ă��܂��B�����܂ł��Q�l�����Ƃ��A���g�̏o�g��w���\�ɓ����Ă��Ȃ�����Ƃ����č��Ƒ����E������������߂�K�v�͌����Ă���܂���I
���ƌ������Ƃ��ĕK�v�Ȏ����ł���Љ�v���ɑ���ӎ��̍�����A�g�D�l�Ƃ��Ă̋�������l�Ԑ��Ȃǂ��ʐڎ��ɏd�v���ڂƂ��ĕ]������܂��B
LEC�ł͑O�q�̂Ƃ���A�u�`�ɂ������b�\�͎���������Ȗڑ��ł͂Ȃ��A�ʐڑ�̃t�H���[���������Ă��܂��B�܂��A���Ƒ����E����������ڎw���ɂ͕s���Ƃ������ɁA�����I�ȃJ���L�������ō��ƈ�ʐE�����肵�Ėڎw�����u�����E����7�F3�R�[�X�v���������܂��B
2023�N�x���ƌ������̗p�����E�����i�t�j�̍��i�Ҕ��\ 2022�N�x���ƌ������̗p�����E�����i�呲���x�����j���{�敪�̍��i�Ҕ��\ ���Ƒ����E��u���̏ڍׂ�
���Ƒ����E�͂����H�J���ɂ���
�c�Ǝ��Ԃ̒������N���[�Y�A�b�v����邱�Ƃ�
���Ƒ����E�ƌ����Ό����Ƃ����C���[�W���蒅���Ă���A���[�N���C�t�o�����X��]�ފw���ɂƂ��Ă͕ǂ�������ʂ����Ȃ�����܂���B�l���@���A�E�������I�����w���ւ̈ӎ������ł��A���ߋΖ���[��E�����ɋy�ԋΖ��̑�����A����W�̋Ɩ��̑�ς����A���ƌ�������I�Ȃ��������R�Ƃ��ċ�����w���͑����A�����E�̎��E���̖�R�������W�O���Ԃ���c�Ƃ����Ă���A�Ƃ�������������܂��B
�����������A�J�����̉��P�ւ̎��g�݂����i
���݁A���ƌ����������E�̎l���͌����X���ɂ���A���̈���Ɍ���������ƌ����Ă��܂��B�l���@���A���̏܂��āA�I�Ƃ��玟�̎n�Ƃ܂łɈ��̋x�����Ԃ�݂���Ζ��ԃC���^�[�o�����x��A�t���b�N�X�^�C�����̊g�[�A�e�����[�N�̕��y��Ȃǂ𐄐i���邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B
���ꂼ��̏Ȓ��̃~�b�V�����̈Ⴂ
������
- �n�������A�ʐM�A�s���]�������l�ȗ̈�Ŋ���
- �s���g�D�A�s���]�����s���g�D�݂̍���ɂ��Ă̗��āA���������x���B
- �n���������s���������̐��i��A�n�������A���h�A���v�����s���B�n���s�����B
- �d�g���̊Ǘ����d�g�̎��g������ƂɊ��蓖�Ă�A���ʐM��Ƃ̊ē��s��
�@����
- �����ǁ��o�L�A�ːЁA���Г������Ɋւ���Ɩ��A������{�@���̐����Ɋւ���Ɩ����s��
- �����ǁ������{�݂̓����A����e�ҏ����ɂ��Ă̎w���E�ēA�V�����������@�̗p������
- �ی�ǁ����ߕ����Ɋւ���Ɩ��A�ی�ώ@�A�ƍߗ\�h�����A�ƍߔ�Q�҂�̎{��
- ��b���[�{�݉ہ��@���ȊNJ��̎{�݁i�@���ǁA���@���A�Y�����Ȃǁj�̈ێ��Ǘ�
�O����
���S�ۏ�A�o�ϊO���A���ۋ��́A�}���`�O���A�p�u���b�N�E�f�v���}�V�[�A���ۖ@�W�̗l�X�ȋƖ��A�����I�Ɂu��g�v�ƂȂ�B
������
- ���L���������g���Čo�ώЉ�ɒʂ������Ƃ̃O�����h�f�U�C����`��
- �����ւ�n�������ǂł̋Ζ��ɉ����āA�C�O���w��C�O�Ζ�������A���l�Ȍo�����ł���
- �\�Z�Ґ��A�Ő����A�������Z���A������Z
- �}�N���o�ϐ���A���L���Y�Ǘ��A���ۊǗ��A�ב֊Ǘ�
�����Ȋw��
- ����s���A�Ȋw�Z�p�s���̕��L������Ŋ���
- ���s�̋���ے��̓W�J�A��w���v�A���U�w�K�A���w�Z�p�i�F���J���j
- �X�|�[�c�U��
- �����|�p����
�����J����
- �u���̂��v�Ɓu�l���v�����߁A�킪���݂̍����n��
- ���������̏d�v���L��ȕ������x����C����S���A�l�̒a������ٗp���o�āA�V��܂ō����̈��S�Ɗ��͂������炷
- ��Õی��A�N���A���ی��A�����A�����̌��N�ƈ��S�̊m�ہA�������̐����A�ٗp�̑n�o�E����Ȃǂ̐���̗��āA���{���s��
�_�ѐ��Y��
- �����́u�H�v�Ɓu���v�𖢗��Ɍp��
- �_�ѐ��Y�Ƃ�H�i��Ƃ̍X�V�A�n��o�ς̊������A���y�E���R���̕ۑS�ȂǑ���ɂ킽�鐭��ۑ�Ɏ��g��
�o�ώY�Ə�
- ����Ɛ��E�����ʂ��ă^�C�����[�Ȍo�ϐ�������{
- ���n�E���n�⎎���敪�ɊW�Ȃ��A�K���ƊS�ɉ����đ��l�ȕ����ɔz���B
���Ɨ\�Z�A���������A�@�č���Ȃǂ��܂��܂Ȑ���c�[���̗��āA���s�Ɍg���B
���y��ʏ�
- �Z�݂悢���y���`�����ĖL���ȍ�������������
- �n��̃~�N���Ȍ��ꂩ�獑�ی��̕���܂ŁA����ɂ킽��t�B�[���h�Ŋ���
����
- �����ւȂ��Ă����\�n���E���̂��E���炵
- �����̑��l���������炷�j�[�Y�ɑΉ�
- �����{��k�Ђւ̑Ή��A���q�͂̋K��
- ���Ȓ���n�������̂ւ̏o��
- ���ۋ@�ււ̔h��
�h�q��
- ���E����������ē��{�̈��S�ۏᐭ���S��
- �O���[�o���Ȏ��_������S�ۏᐭ���Nj�
�f�W�^����
- �f�W�^���̊��p�ɂ��A���l�ȍK���������ł���Љ��ڎw��
- ���̏��V�X�e���A�n�����ʂ̃f�W�^����Ղ̐����A�}�C�i���o�[���x�S�ʂ̊�旧�ĂȂ�
���t�{
- �o�ύ����^�c�A�q��āA�j�������Q�擙�̎i�ߓ�
- �o�ύ�������ˌo�ύ��������c
- �������w�Z�p�˃C�m�x�[�V�������i
- �h�Ё˒����h�Љ�c
- ����U���ˎY�ƐU����
- �����Љ�̎����ˏ��q����A�q��Ďx���A���E����
- �j�������Q��ˏ����̊������i��
�x�@��
�l�̐����E�g�̂���Y�̕ی�ƌ����̈��S�E�����̈ێ���ړI�ɑS��29���l�̐E����i����x�@�g�D�̒����Ƃ��āA�e�퐭��̊��E���č�Ƃɓ�����ƂƂ��ɁA�s���{���x�@�̎w���E�ē��s���B
���Z��
- �o�ς̐S������
- �䂪���̋��Z�@�\�̈��萫�̊m�ہA���Z���x�Ɋւ����旧�āA��s���͂��߂Ƃ��閯�ԋ��Z�@�֓��ɑ��錟���ƊēA�،�������̊Ď���
��������ʂ��A�䂪���̋��Z�@�\�̈��萫�̊m�ہA�a���ҁA�ی��_��ҁA�L���،��̓����ғ��̕ی�A�y�ы��Z�̉~����}�邱�Ƃ�C���Ƃ��Ă��� - �ٌ�m�E��v�m����Z�@�֏o�g�ҁA���Ȓ�����̏o���҂Ƒ��ʂȃo�b�N�O���E���h���������҂ƂƂ��ɁA�d��������
���Ƒ����E�����@���i�҂̐�

���Ƃ��Ɛ����ɋ���������A��������s���ɋ�����������������ڎw���܂����B�s���ɂ��A�n�����獑�Ƃ܂ŕ��L������܂����A�����̐l���̒��ŕς��������Ƃ��o�Ă����Ƃ��ɁA��̃��x���Ŏd�������Ă������������ς��₷���ƍl�����Ƒ����E�Ƃ����`�őI�т܂����B
��y�����炢�낢��Ƃ��b������������ƁA�F���M�������Čg����Ă���d�������邱�Ƃ���A���Ƒ����E��I�����Ă悩�����Ǝv���܂��B

LEC��I���R�́A���Ȗڂł���@���n�̎��Ƃ̎����ǂ��������Ƃł��BLEC�̎��Ƃ́A����������Ƃ����d�v�E�p�o�ȂƂ���ɃX�|�b�g�āA�ɋ}�̂���i�ߕ������Ă���邽�߁A�������g���ǂ����d�_�I�Ɋw�K���ׂ����Ƃ������o�����R�Ɛg�ɂ��A��Ɏ����Ŗ�艉�K�Ɏ��g�ލۂɂ����ɖ𗧂��܂����B
�܂Ƃ�
���Ƒ����E�͌����������S�̂̒��ł��œ�ւł����A�҂̐���͊g�債�A�ȑO�ɔ�ׂĂ�葽���̊w���Ƀ`�����X���J���Ă����Ԃɂ���܂��B�d���̓n�[�h�ŁA�ӔC���d��ł����A�������d���Ɍg����M�d�ȐE��ł�����܂��B�ŋ߂͍��ƈ�ʐE��n���㋉�ƕ��肵�Ȃ������l�������̂ŁA�����œ����A�K�͂̑傫���d���Ɍg��邱�Ƃɖ��͂�������Ȃ�A���������Ă݂鉿�l�͑傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
LEC���I��闝�R
- LEC���I��闝�R
- 30�N�ȏ�A���N�����̍��i�҂�y�o�ł��闝�R��LEC�ɂ͂���܂��B
- ���i�ɓ������͂̍u�t�w
- �S���Ō�������ڎw�����̂��߂Ɍo���L�x�Ȏw���̃v�����u�`���s�Ȃ��܂��B
- Web�K�C�_���X�m��������n
- �������Ɋւ���m����[�߂邱�Ƃ����i�ւ̑����B�킩��₷��������܂��B
- ���i����
- ��ʍ��i��ڎw���Ȃ�LEC�I�I���N�����̍��i���͂��Ă��܂��B
- ���i�̌��L
- LEC�Ō����������ɍ��i���ꂽ��y���i�҂̐��B�w�K���@���̎Q�l�ɂ��Ă��������B
- ����ŃI�����C����u�I
- LEC�ł͎���ɂ����܂܂�Web�����p�����E��u���k�A�������J�u������u�ł��܂��I