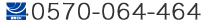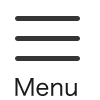��6��10���i�j��菇�����J�I��
�撣�邠�Ȃ��ցALEC�u�t�w����̌��チ�b�Z�[�W�������肵�܂��I���b�Z�[�W�͈�u�t�����ԂɌ��J�������܂��̂ŁA�w�K�̍��Ԃɂ��Ђ������������B
| �� | �� | �� | �� | �� |
|---|---|---|---|---|
| 6/10���J | 6/11���J | 6/12���J | 6/13���J | |
![�]�� �T�V LEC��C�u�t](/common_img/teacher/81920_50_50.jpg) �]�� �T�V�u�t �]�� �T�V�u�t |
 ���� �T�u�t ���� �T�u�t |
 ���c ���F�u�t ���c ���F�u�t |
 ���c ����u�t ���c ����u�t |
|
| 6/16���J | 6/17���J | 6/18���J | 6/19���J | 6/20���J |
 �n�� �M�K�u�t �n�� �M�K�u�t |
 ���� �W��u�t ���� �W��u�t |
 ���� ���@�u�t ���� ���@�u�t |
 ���� �I�u�t ���� �I�u�t |
 �n�� ��O�u�t �n�� ��O�u�t |
| 6/23���J | 6/24���J | 6/25���J | ||
 �{�� ���u�t �{�� ���u�t |
 ���� ���u�t ���� ���u�t |
 �[�y ���a�u�t �[�y ���a�u�t |
�[�y�u�t����̌��チ�b�Z�[�W

���悢��_�������ł��B
�����̂Ȃ��悤�Ō�܂ł�������Ɓu�����v���āA�{�Ԃł͈ȉ��̂��ƂɋC��t���ėՂ�ł��������B
- ������O�̂��Ƃ���O�ɏ���
�_���ɂȂ邱�Ƃ������܂��傤�B�����̈ӌ���V�������Ƃ������Ă��_���ɂ͂Ȃ�܂���B
�F���A���������Ă������Ƃ������܂��傤�B
�����u�ςȑM���v���������Ƃ����痧���~�܂��Ă��������B�u����Ȃ��Ƃ�v������Ă���̂��H�v�Ƃ������Ƃł��B
�{�����́A�u����������v�Ƃ悭�����܂����A�����̒ʂ�ɏ����Ă������Ƃ������Ă��邱�Ƃ����i���ĂւȂ���܂��B - ����Ɋ��
�V�����^�C�v�̖�肪�o�邩������܂���B�悭�킩��Ȃ���肪�o�邩������܂���B
����ǂ��A�Z��������˔j���ꂽ�F����ɂƂ��āA���ɂ��_�ɂ�����������Ȃ����Ƃ��o��͂��͂Ȃ��ł��B
�����ŏ��߂Ďv���������Ƃ͏����Ȃ����Ƃł��B�K������܂łɂ���Ă������ƁA�m���Ă��邱�Ƃ̒m�����u���p�v�u���p�v�ł��Ȃ����A�����āu�v�ʼn��Ƃ��Ȃ�Ȃ����A���̎p����Y��Ȃ��ł��������B
�����̍l���������̂ł͂Ȃ��A�u�F�������牽���������H�v���l���Ă��������B���ȗ��ł͂Ȃ��A�u����Ɋ��v�p���ł��B - �݂�ȏ����Ȃ��獇�i���Ă������̂ł�
�����Ŏ��s���Ă��ӏ��E���W������܂��B�ӏ��Ŏ��s���Ă����W������܂��B�݂�ȁA�~�X�����Ȃ��獇�i���Ă������̂ł��B�����̐l�Ȃ�Ă��܂���B�����܂ł����̎����͑��Ε]�����Ƃ������Ƃ�Y��Ȃ��ł��������B�������ꂵ���Ƃ��́A�݂�ȋꂵ���̂ł��B����ł��A���Ƃ������C�����������A����܂ł���Ă������Ƃ����Ƃ��g���A�Ɋ��Y���������l���Ō�ɏ��܂��B
�Ō�܂ŊF����̌������F���Ă��܂���
�����u�t����̌��チ�b�Z�[�W

�_�������͐悸�͖�蕶����������Ɠǂ݁A�������̐搶�̖₢�ɃX�g���[�g�ɂ������Ă����܂��傤�B
����Ă�����悤�ȉ͕K�v�ł͂���܂���B��������{�ɒ����ɁB�܂����ԈႦ�Ȃ��B���݂̎����Ȃ����ŏ\���ɍ��i�ł���͂��ł��B
�܂��A�z�_�ɏ]�����L�ڗʁB�܂�����ɕK�v�ȍ��ڗʁB����ɋC�Â�����Ȃɍ��i�͓���͂���܂���B��l�ł������̕������i�ł���悤�ɋF���Ă��܂��B�撣���ĉ������B
�ٗ��m �������
�{���u�t����̌��チ�b�Z�[�W

����܂ŋ�����Ă����搶�̋������т��Ă��������B
�����u���Ȃ��l����܂��B
�̒ʂ��������������Ă���l����܂��B
�Ȃ����Ǝv���܂����H
�̒ʂ�����������S�|���Ă���ƁA���R�Ƙ_���ɂ��\��邩��ł��B
�܂�A�u�_���ɂȂ��Ȃ���Ȃ����̒ʂ��������������Ă��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B
����́A�u�_�������Ɏ邽�߂̋ɈӁv�Ƃ��ł͂Ȃ��A�P�ɕ����̖{���ł��B
�n�Ӎu�t����̌��チ�b�Z�[�W

- 1�D����
- �i1�j�����ɘ_���������ł��邱�ƂɊ���
- �i2�j�������Ă��ꂽ�l���v���o��
- 2�D�S��
- �i1�j�Z���ɗ��������Ԃ̕��܂ŔS��
- �i2�j�p�j�b�N�ɂȂ�����[�ċz
- �i3�j���m�̈�s��聨�u�����E��O�v�u���n��v�u���W�v�ŏ���
- 3�D�Y���
- �i1�j�I������Ȗڂ͖Y��Ď��̉ȖڂɏW��
- �i2�j�_���̎��͖Y��đI�������q��ɏW��
��蕶�̖@�I�ȈӖ���T��`�Ŗ�蕶�ƑΘb���A�_�����ł��Ȃ��l�ɂ��v����y���A�܊p�̋@��ł�����A���͂������C�����Ŋy����ł��������B
�����u�t����̌��チ�b�Z�[�W

����͕ς���Ă��A���i�̖@���͕ς��܂���B
- ��Ԗ�肱���T�d��
����܂Ō������Ƃ̂Ȃ��^�C�v�̖��͍��ۂ����߂܂���B���ۂ����߂���Ƃ́A�ߋ���ⓚ���A�͎��ł������Ԗ��ł��B���i������͊m���ɂƂ��Ă��܂��B�����炱���A��Ԗ��͐T�d�ɂ����܂��傤�B - �Z���`�����^���ȋC����
�O�̂߂�߂��č�������̂��悭����܂���B���̒����^�����ɂȂ�����A����܂ł̓��X���v���o���Ȃǂ��āA�����Z���`�����^���ȋC�����ɂȂ��Ă݂���悢��������܂���B�����������玎���ɖ߂�̂ł��B - �Ō�܂Łu�ǂ��C���[�W�v��
�g�[�^���̎������Ԃ��l����ΒZ����������������ł��B���W�@�̍Ō�̐ݖ�܂ʼn����҂��Ă��邩������܂���B�����炱���A�Ō�܂Ŗ��f�����A�Ō�܂Ŋ�]�������āA�Ō�܂Łu�ǂ��C���[�W�v�ł����܂��傤�B
�����u�t����̌��チ�b�Z�[�W

�_�������A�撣���Ă��������I�I
�_�������˔j�̔錍�́A���̓�Փx�Ɋւ�炸�A�ȉ���5�ɏW��Ă���Ǝv���܂��B
- �i1�j�u�p�o�̒m���v
- �i2�j�u�f���ɍl���A����v
- �i3�j�u�z�_�ɑ���L�ڗʁA���Ԕz���v
- �i4�j�u���Ε]���̎����v
- �i5�j�u�����̃����^���͎����ŃR���g���[������v
�������́m���U�n�́A�K���u�ŏI�Łv�܂Ŋm�F���邱�ƁI
��ӂ����Â炢���ɂԂ�������������x�ݎ��Ԃɕ���������͂̐��ȂǁA���x�����x���u�����^���v���h���Ԃ���Ǝv���܂��B
���̂悤�ȂƂ��́A�[�ċz�����āA�w�����܂Ŋ撣���Ă����w�́x�wLEC�̐搶���ɏK���Ă������M�x�w�F������������Ă���Ă�����X�̑z���x���v���o���A�w���v�I�I�Ƃɂ����Ō�܂ł�肫��I�I�x�ƁA�S�ɐ��������Ă����āA�C�����𐮂��Ă��������B
�������ɊԈႢ�ɋC�Â��Ă��A���i�ʂ�ɏ����Ȃ��Ă��A�w�Ō�̍Ō�̍Ō�܂Łx��ɒ��߂Ȃ����ƁI����Ɏ����ō��ۂ��l���Ȃ����Ƃ��ƂĂ��d�v�ł��I
���ۂ����߂�̂́A�F����ł͂Ȃ��A�w�������̍̓_�x�Ɓw���̘͂_�����̂ł���x�ł��B
���M�ƗE�C�������āI
�ْ���s���́A�{�C�Ŋ撣���Ă����I
���O���̋M�d�Ȏ��ԂɃ��b�Z�[�W��ǂ�ł��ꂽ�F���A���N�w�_�����i�ʒm�̃n�K�L�x����ɂ��邱�Ƃ�����Ă��܂��I
�����u�t����̌��チ�b�Z�[�W

���悢��_�������ł��ˁB
����܂Őςݏd�˂Ă����w�͂��������ԂƂ����A���������K��܂��B
�_�������Ɏ���܂łɋ]���ɂ������̂͑���������������܂���B
���̐��ʂ�������ꂸ���M���������������Ƃ���������������܂���B
����ł����߂邱�ƂȂ��w�͂𑱂��Ă���������M�����܂��傤�B
�[�~�ⓚ���Ȃǂɂ����Ď��s�̌������ꂽ���͏��Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B
�{�����ł́A�������瓾��ꂽ���̏������Ă������̂��܂߂āA���Ȃ��̎��͂��o�����Ă��������B
���͂��o���邽�߂ɂ́A�C���������邱�ƂȂ����i�ʂ�W�X�Ɩ����������Ƃ��厖�ł��B
��Ӕc���ɂ͒��ӂ����A�Ⴆ�Γ��t���邢�͌����Ώۂ̏o��┭���ȂǁA�₢�ɐݒ肳�ꂽ���̏�����T�d�Ɋm�F���Ă��������B
�̒��ɂ͏\���ɋC��t���āA�S���̂����N�ȏ�ԂŖ{�����ɗՂ�ł��������I
�������Ă��܂��I
�n��u�t����̌��チ�b�Z�[�W

�Z��������˔j���Ă����܂ŒH�蒅���������A�Z���Ə��Œ��܂������A�܂��͂���܂Őςݏd�˂Ă����w�͂Ɏ��M�������āA�S�͂��o�����Ă��������B
�_�������͒Z�������ƈႢ�A��萔�������Ă��邽�߁A��������̓ǂ݈Ⴂ���傫���e�����邱�Ƃ�����܂��B�����炱���A�ł炸�ɖ�蕶�J�ɓǂݎ�邱�Ƃ���������ł��B
��蕶�ɂ͕K���A�̎����ƂȂ�u�g���K�[�v���B����Ă��܂��B���̃g���K�[�������o���A�������獀�ڂ�I�m�ɏE���グ�Ă����A���i���Ă͎��R�Ƒg�ݗ��Ă���͂��ł��B
���i���ĂɁA���Ƃ������_�q���Ȏ��_���K�v�Ȃ킯�ł͂���܂���B����Ă��邱�Ƃɑ��āA��{�I�Ȓm���Ɋ�Â��A�ؓ��𗧂Ăĕ�����₷���_�q���邱�ƁA����u������O�̂��Ƃ���O�ɏ����v���Ƃ������A���i�ւ̍ł��m���ȓ��ł��B
�_�������͑��Ε]���ł��B���̎����L�ڂ���ł��낤��{�I�Ȏ������A���������āA���J�ɁA�m���ɋL�q���Ă��������B���ꂪ��Ԃ̍��i�ւ̋ߓ��ł��B
�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A��蕶�ɂ͕K���������q���g�A�g���K�[������܂��B����܂Őςݏd�˂Ă����w�K�Ƃ����g�̗͂�M���A�q���g����肭�E���A�������g�̃x�X�g�̓��Ă��쐬���ĉ������B
�݂Ȃ����͂��ő���ɔ������A���i�̉h������ɂ���邱�Ƃ�S�������Ă���܂��B�撣���Ă��������I
���c�u�t����̌��チ�b�Z�[�W

���悢��_�������ł��B
�����̓����܂ŁA
��Ɏ�I�Ƃ����ǂ��C���[�W���������������܂��傤�B
1���ł������̎��Ԃ��m�ۂ��āA
����܂ł���Ă�����N���̕��̑��d�グ����肫��܂��傤�B
���d�����Z�������A�v���悤�ɕ����i�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ͏ł肪��邩������܂��A
����ȂƂ��ɂ͕��č\�����S�̕��ɐ�ւ��铙�ŌJ��Ԃ��ĉ��K�����āA
�S���ʂ̒m��������Ȃ��m�F���āA���M��t���܂��傤�B
�����āA���O���̓����E�͎������p���āA�{�Ԃ̃C���[�W��݂͂܂��傤�B
�܂��A�{�����ŗ͂��ł���悤�A�̒��Ǘ������S�ɂ��Ă����܂��傤�B
�{�����ł͕K���A
�킩��Ȃ����A���������Ƃ��Ȃ���肪�o�肳��܂��B
����ȂƂ������A�ł炸�A�܂��͐[�ċz�����āA
��蕶������x�ǂ�ŁA�o��Ӑ}�𐳊m�ɔc�����܂��傤�B
�����āA��������O�̏��ɋL�ڂ��邱�Ƃɗ��ӂ��āA
���̎����K�������Ă���Ǝv���邱�Ƃ𗎂Ƃ��Ȃ��悤�ɏ����܂��傤�B
��{�I�Ȓm���́A����܂łɂ�������Ɛg�ɂ��Ă���̂ŁA
���������ėՂ߂A�����Ə�����͂��ł��B
�܂��A�{�����ł́A
��̉Ȗڂ������I��������ؐU��Ԃ炸�ɁA
���̉Ȗڂɓ����ւ��܂��傤�B
���Ȃ�������Ǝv�������́A���̎��ɂƂ��Ă�������ł��B
���̉ȖڂŔ҉�Ηǂ��̂ł��B
����܂œw�͂��Ă���������M���āA�ޏk���Ȃ��ŗ����������Ă��������B
�Ō�̍Ō�܂ł�����߂Ȃ��ŁI
�����Ɨ͂��ł���͂��ł��B
�F�����l�ЂƂ�̍��i���ق�Ƃ��ɋF���Ă��܂��B
�撣���Ă��������B
���c�u�t����̌��チ�b�Z�[�W

�܂������ɍ��i���邽�߂ɂ́A�̒��Ǘ������ł��̂ŁA�̒�������ʂ悤���C��t���������B
�����āA�ߔN�ٗ̕��m�����́A�ȑO�ɔ�ׂĎ҂̐l���������Ă�����̂́A�������s�̎����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��l�����܂��B
���̂悤�ȏ�_���{�������O���ɂ����āA���ɗL�����p�ł��鍇�i�̔錍�����`�����܂��B
���̊F����ɂ��`�����������Ƃ́A�{�����́u�T�v���C�Y�v�ɘf�킳��Ȃ��悤�ɂ���A�Ƃ������Ƃł��B
�T�v���C�Y�Ƃ́A�o��`�����V�X���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�A��̂Ȃ��݂���������Ɋւ���o�肪����邱�ƂȂǁA�����˘f�킹��o�������w���Ă��܂��B
�T�v���C�Y�������Ă��A�u�m���Ă��邱�Ƃ����o�Ȃ��͂��v�A�u�������ł��Ȃ����͑��̐l���ł��Ȃ��͂��v�Ǝv���Ď����̎����Ă���͂��ő���������ĉ������B
���Ƃ͈ȉ��̘_���������ō��i�_�����錍�����s����A���i�͌����Ă��܂��B
- �u�����̖{���𑨂��邱�Ɓv
��蕶��ǂލۂɂ́A�����ψ��̗���ɗ����āA�����ψ�������u�������̂���c�����܂��傤�B
�����ψ��̐u���������́A�ߋ�����������Ƃɂ���Ēm�邱�Ƃ��ł��܂��B - �u���i���₷�����Ă̏�������g�ɂ��邱�Ɓv
���i�_����邽�߂ɂ́A�����ψ����ǂ݂₷�����Ă��쐬���邱�Ƃ��d�v�ł��B
�ǂ݂₷�����Ă��쐬���邽�߂ɂ́A���ڂ��ƂɃ^�C�g�������A�ł������ꕶ��3�`5�s���x�̒Z���ɋ���ď������Ƃ������߂��܂��B - �u���������̎��Ԕz�����v�悵�Ă������Ɓv
�Ȗڂ��ƂɁA�����œ��č\�������āA�����œ��Ă��쐬����̂��A�������O���܂łɌv�悵�Ă����܂��傤�B
���̂��߂ɂ́A���i�̓��ė��K�ŁA���������č\���y�ѓ��č쐬�ɂǂꂾ�����Ԃ�������̂���m���Ă����K�v������܂��B
��L�錍�����s���āA���N�̘_����������˔j���܂��傤�I
�����u�t����̌��チ�b�Z�[�W

�v�̂ɂ��A�ǂ��ɂ��ڂ��Ă��Ȃ����Ƃł����A�����^���̋����������Ȗڂ̂ЂƂ��Ǝ��͎v���Ă��܂��B
���X�̕����炢�Ƃ��A����Ȗ��ɓ��������Ƃ��A�����̓_�����悭�Ȃ������Ƃ��A��ɍ��i���悤�Ƃ����c�̋����́A�����̔w���������āA�����J���Ă���Ă����͂��ł��B�݂�Ȃ��������v�������Ȃ���A�ٗ��m�ɂȂ��Ă��܂��B
��ςȂ��Ƃ�����Ǝv���܂����A����ȂƂ������A����ǂ��͎̂�����������Ȃ��A���̎��ɂ͐�ɕ����Ȃ��A����ȋ����C�������v���o���Ă��������B������邱�Ƃ��A���������̎����Ɏ��M���������Ă����͂��ł��B
���܂œw�͂��Ă����F����Ȃ�A��ɂł��܂��I�Ō�܂ʼn������Ă��܂��I�I
�]���u�t����̌��チ�b�Z�[�W
![�]�� �T�V LEC��C�u�t](/common_img/teacher/81920_160_160.jpg)
�O���������A������M���Ė]�߂A�_���{�����ŏI���i���Ղ��I�I
- �[�~�A������蓙�̏T�P�̏������݂͕K�{�A�ߋ��P�N�̊w�K���e�̃t�H���[���s
�`����܂ł̊w�K�͏��Ȃ��Ƃ��{��������70���`80�����J�o�[�` - �{�����Ɍ������`�x�[�V�������ō����ɒB����悤�S�g���ɒ���
�`���������܂ł̐��������ݔ\�͂����ߓ����傫�ȗ͂ƂȂ�` - �{���������͖�蕶���̑�ӂ��Œ�3��͓ǂ�
�`�u���߂��I�v�͒��ӁI�I��Ӕc���͑z���ȏ�ɏd�v�B��ӊO���͒v�����`