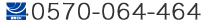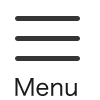行政書士の仕事内容や魅力は?資格の将来性や活かし方
更新日:2022年9月15日
作成・監修者:二藤部 渉 LEC専任行政書士講師
- 目次
- 行政書士の業務内容
- 官公署に提出する提出する書類などの作成業務
- 官公署への手続き代理業務
- 相談業務
- 行政書士の独占業務
- 共同法定業務
- 行政書士の働き方
- 弁護士事務所で働く
- 一般企業の法務部で働く
- 独立開業
- メリット・デメリット、向き不向き
- 広がる行政書士の職務領域!
- 相続等の相談
- 中小企業のコンサルタント
- 他資格へのステップアップ
- 行政書士として働く注意点(”非弁行為”)
- 行政書士として働くのはキツイ?
- 行政書士の将来性は?
- デジタル時代に求められる資格
- 他資格と併せ持つことで広がる仕事の幅
- 合格後も勉強は必要
- まとめ
行政書士の業務内容
官公署に提出する提出する書類などの作成業務
行政書士は、官公署に提出する書類の作成、その相談や官公署に提出する手続きについて代理することを業とします(行政書士法1条の2第1項)。
依頼人からの依頼に応じて、建設業、飲食店、農地転用、古物商などの営業許可申請に必要な書類を作成します。
官公署への手続き代理業務
行政書士は、官公署に提出する書類の作成、その相談や官公署に提出する手続きについて代理することを業とします(行政書士法1条の2第1項)。
官公署への申請に必要な書類の作成に加えて、代理人に代わり書類を提出する手続きについても代理で行うことができます。
相談業務
行政書士は、権利義務に関する書類について作成と相談、事実証明に関する書類の作成と相談を業とします。
依頼人の依頼をヒアリングし遺産分割協議書、契約書、示談書、告訴状などの書類の作成と相談、各種議事録の作成、履歴書の作成などを行います。
行政書士の独占業務
行政書士の業務は、報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を作成することとされています(電磁的記録の作成も含みます)。
ただし、行政書士であれば、それらの書類がいかなるものでも作成できるということではなく、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません(行政書士法1条の2第2項)。ここにいう「他の法律において制限されているもの」とは、いわゆる「士業」に関する法として弁護士法・司法書士法・税理士法・社会保険労務士法などがあげられます。
共同法定業務
行政書士法は1条の2第2項は以下のように規定しています。
第1条の2(第2項)
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
この条文は、文字通り読めば、他の法律によって制限されている書類作成については、行政書士は行うことができないという規定ですが、その反対解釈および行政書士法19条から、他の法律によって制限されていない限り行政書士は書類作成業務を独占業務として行うことができるということになります。これが行政書士の広い独占業務を根拠付ける規定となっています。また、他の士業に関する法律によって、共同法定業務として許容されているものについては、行政書士の非独占業務として認められると解されています。具体的に、他の士業法によって共同法定業務として許容されている業務は以下の通りです。
- (1)非紛争的な契約書・協議書類の作成は、弁護士との共管業務とされています。
- (2)著作権ライセンス契約書の作成は、弁理士との共管業務と解されています。
- (3)法務大臣あての帰化許可申請書、検察審査会提出書類の作成は、司法書士との共管業務とされています。
- (4)ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税、石油ガス税、不動産取得税、都道府県たばこ税、市区町村たばこ税、特別土地保有税、入湯税に関する書類作成業務は、税理士との共管業務とされています。
- (5)1ヘクタール未満の開発行為の設計図書を含む開発許可申請書の作成は、建築士との共管業務となっています。これは、都市計画法施行規則第19条で1ヘクタール以上の場合は建築士などの資格要件が定められていることの反対解釈から導かれます。
- (6)労働・社会保険法令上の申請書等、帳簿書類の作成といった業務
1980年(昭和55年)8月末時点の行政書士(社会保険士法施行前の行政書士)に限っては、これらの業務は、社会保険労務士との共管業務となっています。
行政書士試験合格のための対策講座はこちら!
行政書士の働き方
行政書士の監督のもと、官公署に提出する書類の作成やその提出を行うことができるのが「補助者」です。補助者として働くためには、行政書士会に補助者登録されることが必要です。 また、「使用人行政書士」として、行政書士事務所や行政書士法人に雇われて行政書士業務を行うこともできます。
弁護士事務所で働く
いわゆるパラリーガル(法律事務員)として勤務することができます。法律事務所の電話応対などの業務の他、弁護士の指示を受け判例を調査したり、契約書などの法的文書の作成や完成した文書の法的なチェックをしたりといった業務です。関係する法律や類似の判例を調査するなどの調査能力が必要のため、行政書士試験で養った自らの法律知識を使って調査することが必要となります。
一般企業の法務部で働く
他社と何らかの契約をする場合、契約書を作成することが必要ですが、その際に提示する契約書の作成や相手方から提示された契約書の内容をチェックすることが必要です。英語や中国語での契約書の作成やチェックも必要な場合があります。行政書士は一般的な法律知識を持っていますから、このような契約書の作成について、実力を発揮できるでしょう。さらに株式会社の場合、株主総会の準備や運営、議事録の作成なども業務範囲内となってくるでしょう。
独立開業
合格後、すぐに独立することもできます。開業後は全て一人でやらなければならないため、このパターンが一番早く業務を覚えることができるのではないかと思います。ただ、開業後は収入が不安定になるため、色々な要素(仕事はどうやって覚えるのか、業務開始当初は収入が低下することを考慮しているかなど)を考慮しておかなければなりません。
メリット・デメリット、向き不向き
独立開業をせずに、他の事務所で働きながら業務を覚えていくというやり方はある意味で合理的です。わからないことは、事務所の先輩や、士業の先生に直接聞くことができ、業務を覚えることができる絶好の機会になるでしょう。ただ、その事務所が扱っていない業務に関しては知識・経験を得ることができないので、結局独立開業後にはそれらに関しては自分で会得していくしかないことになります。
一方で、いきなり独立開業する場合は、業務のことは一切わからず開業することになります。実は私もいきなり独立開業してしまったパターンになります。初めての業務依頼が来たときはドキドキしながら仕事をこなしたことを憶えています。業務知識に関しては行政書士会の研修会が定期的に開催されているので、その研修に参加することで知識を得られることでしょう。また研修会に参加すれば、参加者は行政書士ばかりなので、仲間の行政書士との交友を広げることもできるでしょう。
以上のように一長一短ですので、ご自分に合った道を選ぶことが重要です。
広がる行政書士の職務領域!
相続等の相談
人がお亡くなりになったときには相続手続が必要になります。お亡くなりになった方の財産は、相続人で協議し分割していくことになります。そして、相続手続には以下のような手続きが必要です。
- 遺言の存在の確認(遺言があれば原則的に遺言どおりに分割することになります。)
- 相続人の確定(相続人にあたる人はだれなのか、戸籍謄本を取得し相続人を調査します)
- 遺産分割協議(相続人が確定したら、その相続人全員で遺産をどのように分割するのか話し合いを行い、各相続人の相続分を確定します。)
- 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議で決定したことを書面にします。)
- 遺産分割協議書の記載されたとおりに、相続分を自己名義に変更(預金や不動産の名義変更手続。登記申請は行政書士業務ではありません。)
以上がおおよそ相続に必要な手続となります。
これらの手続きを一般の方が行うのは、なかなか大変な作業です。一番大変なのは、相続人確定の手続きです。相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまで間断なく続いている戸籍謄本を取得していく必要があります。本籍地がひとつの市町村であれば取得は楽ですが、本籍地が転々していると、その市町村全てで戸籍謄本の取得をしなければなりません。離れている市町村では郵便で取得することになります。これらの取得手続には非常に手間と時間がかかります。行政書士はこれらの手続をサポートすることになります。
令和2年度の日本行政書士会の「行政書士報酬額に関する統計調査」では、遺産分割協議書の作成は平均で約7万円、相続人の調査等の業務で平均約6万円というデータになっています。どちらか一方のみ依頼されることもありますが、両者とも依頼されることが多いので、相続手続を一通り行えば、10万円以上を報酬として受けることができるでしょう。
中小企業のコンサルタント
独占業務である書類作成に付随する形で相談に応じ助言をすることができます。例えば、建設業許可申請書類の作成に関して助言をしたり、飲食店の営業許可申請書類の作成について助言をしたりすることは、依頼者のためになる情報として、積極的に提供していくことは依頼者に喜ばれるでしょう。そういった意味でコンサルタント的な業務をしていくことが可能です。
他資格へのステップアップ
行政書士試験の学習で得た法律知識を生かして、司法書士試験に挑戦する方が多いです。司法書士試験と行政書士試験では、憲法、民法、商法・会社法が共通しています。初めて法律を勉強する方に比べれば、理解の部分で大きなアドバンテージがあるといえます。また、行政書士と司法書士のダブルライセンスを活かせば、非常い広い業務を扱うことができます。
行政書士として働く注意点(”非弁行為”)
弁護士の業務は、法律事務を行うことであり、裁判所における訴訟事件、非訟事件における行為、その他一般の法律事務などを職務とします。すなわち紛争性のある業務は行政書士が行うことはできません。弁護士法72条では弁護士でない者の法律事務の取扱を禁止しており、違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(弁護士法77条3号)。業務の依頼を受けるときは気を付ける必要があります。
行政書士として働くのはキツイ?
行政書士試験に合格後、行政書士登録をしてもすぐに業務をすることができるわけではありません。自分が行政書士登録をして、業務ができる状態になっていることを知っているのは、恋人や親兄弟・親戚など自分に近しい人のみです。ですから登録後は、積極的に営業する必要があります。安定的な収入を望むのであれば、会社員として働くほうがよいでしょう。業務開始当初に依頼者を探すことにはとても苦労するかもしれません。
私の場合は、業務開始当初はディーラーなどの車屋さんに車庫証明の取得代行の手続きをやらせてくださいという形で飛び込みの営業していました。しかし、これはほとんど業務に結びつきませんでした。その後、「相続手続や遺言書作成のサポートをいたします」というチラシを自分で作成し、各お宅にポスティングをしてみましたが、これもうまく業務につなげることはできませんでした。
結局最後に私が行き着いた営業はホームページを作成することです。HP作成の知識やSEO対策の知識もないまま始めました。その後手探りでSEO対策もしてなんとかサイト検索で上位表示されるようになり、そこから初めての仕事につながったときはとてもうれしかったのを憶えています(もう15年くらい前です。)。
業務が軌道に乗るまでは本当に大変です。勤めている会社を辞めて行政書士業務一本で収入を得ていくことを考えているなら、行政書士業務に集中して全力でやっていくという覚悟が必要でしょう。
行政書士の将来性は?
デジタル時代に求められる資格
現在、社会全般で急速なデジタル化が進んでいます。今後もこの流れは続くでしょう。ただ、それで行政書士にできることがなくなるわけではありません。
今まで紙で提出していた書類がデジタル申請に変更される、そういうときにこそ官公庁に対する行政手続の唯一の専門家である行政書士の出番といえます。
いままでの業務に固執することなくデジタル化に対応できるように考え方を変えるとともに、新しいシステムの専門的知識を積極的に取り入れていくようにすれば、行政書士の業務の需要が尽きることはないでしょう。
他資格と併せ持つことで広がる仕事の幅
行政書士は他の資格と併せ持つことで仕事の幅を広げることができます。例えば行政書士は会社の設立に際し、定款の作成ができますが、司法書士の資格を取得すると、法務局への会社設立の登記申請(商業登記)まで行えるようになります。
まずは行政書士の資格を取得することが前提にはなると思いますが、将来、行政書士として仕事をするにあたり必要と感じた資格を取得すれば、業務の幅が拡がり、扱える案件が増え、より多くのクライアントの獲得につながるでしょう。
合格後も勉強は必要
行政書士業務は、さまざまな法律に関わる仕事です。許認可申請においては、その許認可を規律する法律があったり、また契約書や遺言の作成をサポートするようなときは民法の適用を受けたりと、根拠法律を守って業務を行うことが必要です。しがって、新しい法律が施行されたり、法律が改正されたりした場合には、常に自ら学習する必要があります。知識をアップデートできていないと、必要な許可がもらえなかったりして結果的に依頼者に迷惑をかけてしまいます。ですから、行政書士登録した後も常に学習することが必要になってきます。行政書士として業務をする以上は、一生学習していくことが求められるでしょう。
まとめ
行政書士の業務の中のいわゆる「許認可業務」は、1万以上の種類があるといわれています。これは新しい法律が制定されると、それに伴う新しい許認可業務が発生するためです。まだ他の行政書士があまり手をつけていない範囲の許認可申請を業務として受けることができるようになれば、専門性を持った数少ない行政書士としての地位を得ることができ、多くの依頼を得るチャンスが増えるでしょう。行政書士として開業を予定している方は検討してみてください。
行政書士試験合格のための対策講座はこちら!
行政書士へのスタートはココから!
LEC本校一覧(行政書士講座実施校)
この記事の監修者は

にとべ わたる 二藤部 渉 LEC専任講師
| 生年月日 | 1972年10月3日 |
|---|---|
| 最終学歴 | 駒澤大学 法学部 法律学科 |
合格率2.89%だった平成15年行政書士試験に合格し、平成17年にとべ行政書士事務所を開業し、開業とほぼ同時にLEC行政書士講座の専任講師となる。技能実習制度に関わる業務を中心に展開しています。趣味はフットサル、ゴルフ、ゲーム、ガンプラ作成。パグ好きです。