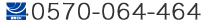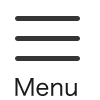ファイナルチェック!絶対に落とせない「かぶり問題」

「かぶり問題」とは、LECを含む受験対策スクール4社の1次模試で、テーマが重複した問題。各社が重要視している最頻出の出題分野を、ぜひチェックしてください。
経済学・経済政策
かぶり度:★★★★
IS-LM分析
- ポイント
- IS曲線の意味、形状、シフトなどが問われる。またLM曲線についても意味、形状、シフトなどが問われる。特に頻出なのではLM曲線が水平になる流動性のわなのケースであり、財政政策にはクラウディングアウトが生じない事や、金融政策が無効であることなど深い問題も多い。IS-LM分析は、景気や金利、政策など日本経済の全体のマクロの状況を理解するために必須の知識である。為替レートや国際収支についての議論もIS-LMを基礎としてる。
- コメント
- 1次突破のためにはIS-LM分析の理解は必須である。よって、試験対策として用語などをしっかりと学習し、内容を理解して1国全体の経済の方向性、とくに、好景気になるのか、不況になるのかを大きく誤らないレベルには到達しなければならない。更に、税制や公共事業などの財政政策の問題、あるいは、日本銀行の金融政策の効果なども試験にでるので、しっかりと理解しておこう。
かぶり度:★★★★
外部経済
- ポイント
- 金銭的外部性と技術的外部性の区別をしよう。また、社会的限界費用と私的限界費用の意味や公害の大きさを図で問う問題は多い。更に、最適な生産量は社会的限界費用で決定されるが、私的均衡としては実現できず、私的限界費用をもとに生産量が決定される自由状態では死荷重が発生する。基本事項だけは、しっかりと学習しておきたい。用語、図、余剰分析、外部性の金額など多彩な出題が行われている。1つ1つ理解していこう。
- コメント
- 外部不経済は、ごみ処理や騒音対策、インフラ整備、環境問題などに関わるテーマである。よって、重要性から見て、外部性が出題されるのは今後も間違いない。受験対策としては、やや難しい所があり、SMCとPMCを使った基本テーマだけでなく、排出権取引制度、炭素税のようなピグー的課税、コースの定理、減産補助金なども出題されうる。最低でも基本テーマだけはしっかりと理解しておきたい。
かぶり度:★★★★
損益分岐点と操業停止点
- ポイント
- 価格がACより上では利潤が発生する。この利潤の大きさを問うとか、ACの最低点が損益分岐点であり、利潤がゼロになること。AVCの最低点は操業停止点であり、価格がこの点になると固定費用と等しい損失が発生する。AVCとACの間では赤字だけど生産は継続する。その理由は固定費用の一部が回収可能であるからである。また、利潤の大きさを答えたり、生産量の決定が限界費用をもとに決定されるなどを支えておきたい。企業行動に関する重要事項が凝縮されているテーマである。
- コメント
- MC、AC、AVCの3つの要素があり、かなり複雑な理論となっている。この点をしっかりと整理して理解・暗記しておく必要がある。ミクロテーマでは難易度の高いテーマであるが本試験では頻出であり、このテーマが確実に得点できることが理想である。ただし、出題側も、いろいろと工夫するので困ってしまう。
財務・会計
かぶり度:★★★★
経営比率分析
- ポイント
- 経営比率分析については、安全性(流動比率、当座比率、固定比率、固定長期適合率)、効率性(総資産回転率、売上債権回転率、棚卸資産回転率、有形固定資産回転率)、収益性(売上高利益率、総資産利益率(ROA)、自己資本利益率(ROE))、生産性(労働生産性、労働分配率)の指標が重要である。
ROE=財務レバレッジ×総資産回転率×売上高利益率、ROA=総資産回転率×売上高利益率 といった総合収益性の式も押させておきたい。
- コメント
- 経営比率分析は、1次試験、2次試験(事例Ⅳ)の両方で出題される最重要論点である。主な指標について、前年度と当年度の比較、業界標準や競合他社との比較、固定資産の売却や借入金の返済を行った場合の指標値の変化といった多面的な出題形式がある、また、直近5年では、生産性の指標、インタレストカバレッジレシオ(支払わなければならない利息(インタレスト)の何倍の利益を稼ぎ出しているかを示す指標)、サステナブル成長率(内部留保のみを事業に投資した場合の純資産の成長率)が出題された。基本的な指標をしっかりおさえつつ、近年出題された指標もおさえてきたい。
かぶり度:★★★★
損益分岐点分析
- ポイント
- 損益分岐点分析の最も基本的な汎用公式は、目標売上高 = (固定費+目標利益)/(1−変動費率) である。ここで、目標利益がゼロである場合の目標売上高は損益分岐点売上高と呼ばれ、損益分岐点売上高 = 固定費/(1−変動費率)となる。①利益を出すための目標売上高は、②損益分岐点売上高と、③(目標売上高−損益分岐点売上高) の和に分解でき(①=②+③)、②÷①を損益分岐点比率、③÷①を安全余裕率という。これらの比率の和は常に100%で、前者は小さい(後者は大きい)方が望ましい。
- コメント
- 損益分岐点分析については、売上高利益率=安全余裕率×限界利益率=(1−損益分岐点比率)×(1−変動費率)という応用公式に関する問題、目標利益を達成した際の総資本営業利益率、傾向分析(収益性の観点からは、「損益分岐点比率」を低下させる ことが改善を意味する)など広く出題されている。また、令和3年度には知識問題として出題された。様々な問われ方にも留意し、複合的な問題に対応できる準備をしておきたい。
かぶり度:★★★★
実物投資
- ポイント
- 設備投資を評価する方法としては、将来キャッシュフロー(将来CF)を現在価値に割引いた上で初期投資額を差し引いた正味現在価値(NPV)がプラスであれば投資すべきと判断するNPV法、正味現在価値(NPV)がゼロとなるような割引率(内部収益率、IRR)よりも資金提供者の期待収益率(資本コスト)が小さければ投資すべきと判断するIRR法、将来キャッシュフローの現在価値を初期投資額で割り1より大きければ投資すべきと判断するPI法(収益性指数法)、将来キャッシュフローで初期投資が回収されるまでの期間(回収期間)が短い投資案件を採用する回収期間法などがある。
- コメント
- 各評価方法の評価基準(NPV法:額、PI法:倍、IRR:率、回収期間法:期間)とそれによるメリット・デメリット、割引率とNPVの関連(割引率が大きくなるほどNPVは低くなる)を確実に覚えておきたい。また、将来CF(各年)については、将来CF=税引後利益+減価償却費=(現金収入収益−現金支出費用−減価償却費)×(1−税率)+減価償却費、あるいは、将来CF=税引後CF+節税効果=(現金収入収益−現金支出費用)×(1−税率)+減価償却費×税率となる。これらの重要公式を確実に覚えておきたい。
企業経営理論
かぶり度:★★★★
多角化
- ポイント
-
多角化とは、企業が既存と異なる事業に進出することを指す。広義には、製造業が小売業に進出するように流通連鎖の川上や川下に進出する「垂直統合」も含む。
関連多角化のうち、資源展開のパターンにより、①集約型と②拡散型がある。
集約型とは、軸となる経営資源を様々な事業に活用することであり、拡散型とは、進出した事業で得た資源を梃子にさらなる多角化を進めることである。
多くの研究結果では、集約型のほうが収益性が高いとしている。
- コメント
-
毎年1題程度出題される頻出論点である。
出題のポイントには、①多角化の動機、②多角化の類型、③多角化の程度と業績の関係が問われやすい。
かぶり度:★★★★
コンフリクト
- ポイント
-
コンフリクトの発生要因には、下記のようなものがある。
①共同意思決定の必要性
→他の部門とタイミングを合わせる必要がある場合
②組織スラックの不足
→限られた資源を奪い合う場合
③非公式コミュニケーションの発達
→目標が分断したり、メンバー間の認識が異なったりする場合
④目標の操作性が低く曖昧
→操作性とは測定可能性のことで、達成基準などが曖昧な場合
- コメント
-
2〜3年に1度程度出題されており、令和元年度、令和3年度、令和6年度などで出題されている。
コンフリクトの発生要因や、コンフリクトへの対処方法などが問われやすい。
かぶり度:★★★★
サービス・マーケティング
- ポイント
-
サービス・マーケティングの関連用語に下記のようなものがある。
・SERVQUAL
ServiceとQualityからなる造語で、サービス品質を測定する指標のことをいう。
・逆さまのピラミッド
素早い顧客対応を行うために、接客担当者に顧客対応に関する権限を委譲し、管理者はそれをサポートすべきという考え方。
・サービスの工業化
標準化や自動化を通じて、サービスの品質の変動性を抑制しようとする考え方。
- コメント
-
毎年1題程度出題される頻出論点である。
サービス財の特性や、サービス・マーケティングのほか、ポイントに記載したような関連用語が出題されやすいため、要点を整理してほしい。
運営管理
かぶり度:★★★★
PERT
- ポイント
-
PERTとは分岐や合流などがある複雑なプロジェクトのスケジュールをアローダイヤグラムといわれる矢線図を用いて表現する手法である。
複数の経路のうち、最も所要時間の長い経路をクリティカルパスという。プロジェクト全体の所要時間を短縮する場合は、クリティカルパス上の作業の所要時間を短縮する必要がある。
また、クリティカルパス上にある複数の作業のうち、最も費用対効果の高い作業を優先して短縮することが有効となる。
- コメント
-
毎年1題程度出題される頻出論点である。
作業リストの内容をもとに、アローダイアグラムを作成し、プロジェクト全体の所要時間や、CPM(クリティカルパスメソッド)を使った最小費用を選択させる問題が頻出である。
かぶり度:★★★
商圏理論
- ポイント
-
商圏理論の問題は、用語の空欄補充の問題や計算問題が出題されるケースが多い。主に下記の3点の内容より出題される。
①ライリーの小売引力の法則
→ある地点から見た小売引力は、都市の人口に比例し、ある地点までの距離の二乗に反比例する
②ライリー・コンバースの法則
→2つの都市の小売吸引力が均衡する商圏分岐点を求めるモデル
③ハフの確率モデル
→周辺の競合状況を考慮し、店舗面積と距離の観点から、ある店舗への出向確率を求めるモデル
- コメント
-
近年は計算問題が出題されるケースも多いため、過去問で出題された内容については整理してほしい。
特に、ライリーの小売引力の法則は解けるようにしておきたい。
ライリー・コンバースの法則やハフの確率モデルも、慣れれば計算できる論点であるが、苦手な方は深追いする必要はない。
かぶり度:★★★★
値入高予算
- ポイント
-
商品予算計画における値入高予算の問題は、計算問題で出題されやすい。
原価値入率とは、原価に対する割合で値入高を求める手法であり、売価値入率とは、売価に対する割合で値入高を求める手法である。
セット販売や福袋などの問題も出題されるが、基本はまず原価を算出することである。原価値入率より売価を求める場合は、原価×(1+原価値入率)、売価値入率より売価を求める場合は、原価÷(1−売価値入率)によって算出できる。
- コメント
-
商品予算計画に関する計算問題は、例年1〜2題程度出題されている。
近年は小売業における予算計画のうち、値入高予算、相乗積、人時生産性が図表読解および計算問題として頻出である。
出題されている内容や観点は、過去の出題例を踏襲しているケースが多いため、過去問演習を通じて論点を整理してほしい。
経営法務
かぶり度:★★★
会社分割
- ポイント
-
吸収分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。これに対し、新設分割とは、1又は2以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
会社分割によりどの権利義務が承継されるかについては、吸収分割契約又は新設分割計画に定めるところによる。
- コメント
-
会社分割では、利害関係人が広範囲に及ぶため、事前開示書面の備置、株主総会の特別決議による承認、債権者に対する官報公告、異議を述べた債権者又は反対株主等に対して弁済や株式買取等の対応が必要となる。
書面の備置や債権者などへの通知・公告について、契約に関する書面等を本店へ備え置く日は株主総会開催の2週間前、また、反対株主への通知や株主総会招集の通知は、総会の1週間前(公開会社は2週間前)に行うとする規定がある。
かぶり度:★★★★
不正競争防止法
- ポイント
- 不正競争防止法は、不正競争となる行為を禁止する法律である。これによって、特許法や意匠法、商標法などではカバーしきれない領域の事柄に対して、法律的な効果を発揮する。不正競争防止法の中でも代表的な、「周知表示の混同惹起」「著名な商品表示の冒用」「商品形態の模倣」「営業秘密の侵害」などはもちろん、「限定提供データ」についても要注意である。なお、「限定提供データ」は、技術上又は営業上の情報を保護するが、営業秘密は含まれない点は注意を要する。
- コメント
-
周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)では、「商品表示性」が問われたことがあった。当該表示が、「商品等表示」つまり、ある商品を示す印として機能している必要があり、種類や方法を問わず、ある事業者の商品又は営業を表示するものであれば保護の対象となりうる。例えば、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれる。他にも「周知性(需要者の間で広く認識されていること)」、「類似性(商品等表示が、同一又は類似していること)」、「混同のおそれ(需要者が混同を起こすおそれがあること)」、といった要件も押さえておきたい。
また、著名表示冒用行為(不競法2条1項2号)では、周知表示混同惹起行為の周知性よりも全国的に需要者以外にも広く知られている「著名性」が必要であるが、混同のおそれは不要である点は注意を要する。
「限定提供データの不正取得」において保護される「限定提供データ」は、①「業として特定の者に提供する」(限定提供性)、②「電磁的方法により相当量蓄積され」(相当蓄積性)、③「電磁的方法により管理され」(電磁的管理性)の3つ要件を満たす必要がある。
さらに、平成30年改正により、不正競争防止法にビッグデータ保護制度が創設された当時は、他者と共有するビッグデータは秘密管理されるものではないと想定していたため、旧法では「秘密管理されていないビッグデータ」のみ保護対象となっていた。しかし、近年、自社で秘密管理しているビッグデータであっても他者に提供する企業実務があることから、令和5年の改正により、対象を「秘密管理されたビッグデータ」にも拡充された(令和6年4月1日より施行されている)。
かぶり度:★★★★
相続
- ポイント
-
平成30年7月に民法の相続分野の法改正があり、改正法では、遺留分返還方法については、遺留分減殺請求という形ではなく、遺留分侵害額の請求となった。
また、改正法では、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産に含めることとなった。これにより、相続人に対し、相続開始より10年以上前に贈与された財産は、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないことになる。
- コメント
-
遺留分侵害額の請求となったことで遺留分を金銭で返還してもらえるのであれば、計算も簡単で不動産が共有になることもなく、従来の事業承継の問題が残るおそれもなくなる。
なお、遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちには準備できない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。
また、相続開始後遺産分割がないまま長期間が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れてしまう。そうすると、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となるおそれがある。そこで、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)によることとなる、とする改正が令和5年4月から施行されている。この点も要注意である。
経営情報システム
かぶり度:★★★★
AI・機械学習(Python含め)
- ポイント
- AIは、人工知能のことで現代において必要不可欠な存在になろうとしている。現代のAIは機械学習から推論された結果を出力することができ、高度な判断、処理が可能となっている。この成果も、ディープラーニングと言われる深層学習の技術が確立したことが大きい。ディープラーニングは、人間の脳神経であるニューロンを模したニューラルネットワークによって作られており、複雑な処理判断が可能となる。最近では画像生成に適したディープラーニングモデルや、文章生成に適したモデルなどの生成AIへの活用も進み、業務においても活用度が高まっている。
- コメント
- AI・機械学習の論点は、ここ数年でも2問ずつほど本試験においても出題がある。この傾向はさらに強まることが予想される。生成AIの活用や、ディープラーニング技術について、さらにはそれを取り巻く社会的な課題(ハルシネーションやディープフェイク)などさまざまな側面での出題があり得るため、幅広く学習しておきたい。Pyhtonなどのプログラム言語としての出題もあり得る。生成AIパスポート試験やG検定などのテキストを軽く見てみるのも対策としては良い。なにより現代のAIの活用について興味を持って接しておいてほしい。
かぶり度:★★★
DX
- ポイント
- DXはデジタルトランスフォーメーションであり、デジタル活用による改革を意味する。単なるデジタル化ではなく、トランスフォーメーション(変革)であることがポイントで、イノベーション創出が目指される。国や自治体なども含めてDXがかなり進められてきた。DXを進めるのに際して、デジタルガバナンスコードやDXリテラシー標準、などのガイドライン系の資料も多く取り揃えられてきている。DXをスムーズに進めるためには、ITリテラシーの高い人材が不足している問題を乗り越え、DX人材の育成やDXそのものの理解の促進、正しいDXの知識・ノウハウも必要である。
- コメント
- DXについての出題の可能性はかなり高い。DXとは何かという単純な問いではなく、DXを進めるための具体的な知識としてシステム開発やプロジェクトマネジメントを絡ませた知識を問うということも考えられる。また、ガイドラインなどの論点としての出題もあり得るため、一筋縄ではいかない可能性もある。しかし、DXに関連するところは重要度も高いため、なるべく幅広く学習しておいてほしい。
かぶり度:★★★
データサイエンス
- ポイント
- データサイエンス分野は、BI(ビジネスインテリジェンス)なども含めたデータ分析分野である。ビッグデータの時代であり、ビッグデータをいかに活用していくかが第4次産業革命期を生きる社会としては必要なことである。国や自治体もオープンデータという形でさまざまなデータ公開に積極的である。これまでのRDBを代表とする構造データだけでなく、文章(自然言語など)や画像などの非構造データを上手に扱い、分析していくことも求められる。この技術を支えているのが、回帰分析や相関分析など統計学を使った知識であり、基本的な統計知識も必要とされる。
- コメント
- 本分野も幅広い論点ということもあり、何かしらの出題の可能性は高い。これまでの試験においても高頻度に出題はされてきている。これがさらなるデータを活用していく時代になった今、これまで以上に重要度の高い論点である。AIによる分析などAIを活用する論点としても考えられる。DXの中でのデータ活用という視点もあり得る。複合的な観点での出題が想定されるため、しっかりと見直しておこう。
中小企業経営・政策
かぶり度:★★★★
経営革新計画
- ポイント
-
【概要】
経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受けることで、日本政策金融公庫の特別利率による融資や信用保証の特例など多様な支援を受けることができる【事業内容】
以下のいずれかに該当する取組(自社にとって新しい取組であれば、他社で採用されているものも対象となる)
①新商品の開発や生産
②新役務(サービス)の開発や提供
③商品の新たな生産方式や販売方式の導入
④役務(サービス)の新たな提供方式の導入
⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用、その他の新たな事業活動【経営目標】
3〜5年の事業期間において、以下の両方を満たす計画となっていること
①付加価値額または従業員1人当たり付加価値額が年率3%以上増加
②給与支給総額が年率1.5%以上増加
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費【支援内容】
①政府系金融機関の特別利率による融資制度等
②信用保証の特例
③中小企業投資育成株式会社法の特例
- コメント
-
【過去問の頻出ポイント】
・経営目標と数値目標、事業期間、付加価値額の公式・計算
・経営革新に該当する事業内容
・支援内容
・根拠法(中小企業等経営強化法)
かぶり度:★★★★
下請代金支払遅延等防止法
- ポイント
-
【法律の適用範囲】
親事業者と下請事業者の資本金額に着目する。①物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託
親事業者:3億円超→下請事業者:3億円以下
親事業者:3億円以下1千万円超→下請事業者:1千万円以下
②政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託
親事業者:5千万円超→下請事業者:5千万円以下 親事業者:5千万円以下1千万円超→下請事業者:1千万円以下【親事業者の義務】
①発注書面の交付義務:委託後ただちに、給付の内容・下請代金額・支払期日・支払方法等を記載した書面で交付する。
②取引内容記録を書類で作成・保存義務:2年間保存。
③下請代金の支払期日を定める義務:受領した日から60日以内かつできるだけ早く
④遅延利息の支払義務:受領した日の60日後から支払日までの日数に年率14.6%を乗じた金額を遅延利息として支払う。
- コメント
-
【過去問の頻出ポイント】
・法律の適用範囲
政令で定める情報成果物:プログラム
政令で定める役務提供:運送、物品の倉庫における保管、情報処理
・親事業者の義務
かぶり度:★★★★
小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)
- ポイント
-
【概要】
小規模事業者は、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低利で日本政策金融公庫から融資を受けることができる【対象者】
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人・個人事業主で、以下の要件をすべて満たす者
①経営指導員による経営指導を原則6カ月以上受けていること
②税金を原則として完納していること
③同一の商工会等の地区内で1年以上事業を行っていること
④商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種であること
【対象資金】設備資金・運転資金
【貸付限度額】2,000万円
【担保・保証人】不要
【貸付期間】設備10年(据置2年)
【金利】低利
- コメント
-
【過去問の頻出ポイント】
・対象者となる要件
・対象資金、貸付限度額、担保保証、貸付期間、金利
・商工会、商工会議所で審査、推薦を行い、日本政策金融公庫の審査を経て融資実行
※今年から貸付期間が設備資金・運転資金共通で10年以内(据置2年)に統一された
中小企業診断士の情報を今すぐキャッチしよう