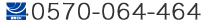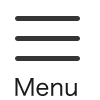【経営法務】難化しても耐えられる「経営法務」の学習法とは
早速ですが、経営法務の試験は一定のサイクルで難化と易化を繰り返しています。直近の年度はそこまで難しくない年が続いているからこそ、受験生の皆様の中には、難化を不安視する方もいらっしゃるでしょう。
そこで今日は、難化しても耐えられるような「経営法務」の学習法についてお伝えしていきます。
今日はコラムということで、いつもの講義のようにまくし立てたりはしませんので、リラックスして読んでいただければと思います。
【1】絶対に基礎的な問題はある→基礎的な問題を確実に仕留める「足腰」
どんなに難化したとしても、テキストレベルで正答を導くことができる問題は必ず出ます。また、テキストレベルで選択肢を絞り込める問題もそれなりに出ます。
このため、基礎的な理解をしっかりしておくこと、つまり難易度が高くなく、頻出の分野や問題は確実に解けるようにインプットとアウトプットをしておくことが大事です。
皆さんは答練や過去問の復習のとき、難易度が高くない問題について、正解したものをそのまま放置していませんか?
全ての肢(アイウエ)について、どれかひとつだけ〇×問題で出てきても正解できるようにして初めて「その問題を完全に解いた」と言えます。
「肢のウがよくわからなかったけど、結論的に正解したからもういいよね」という姿勢はダメです。
基礎的な問題を完全に解ける基礎力こそが、難化のときに皆さんを救う足腰の強さに結びつきます。
【2】リーガルマインド(法的な思考のクセ)をつける→鉛筆を転がすよりも的中率が上がる
難化をした年には「なんやこの問題」という問題が複数出てきます。
そんなときには、リーガルマインドと呼ばれる、法的な思考のクセを身に着けていることが有効打になります。私がいつも講義で連呼しているワードです。
たとえば
「代表取締役は、他の取締役を解任することができる」という文章が出てきた場合、明らかにおかしいことはわかりますね。
もちろん、「取締役の選解任は株主総会の権限だから」というのが正解なのですが、そういうルールがあるからそうなのだ、という理解では変化球に対応できません。
株主総会は取締役よりも偉い。だから株主総会が取締役を選ぶ。
↓
そんな株主総会が選んだ取締役を、代表取締役が勝手に解任できてしまうとすれば、株主総会が取締役を選任できても意味がない(翌日に解任させられてしまう)。
↓
そのため、このようなルールはおかしい。
というような思考回路がリーガルマインドと呼ばれるものです。
こういう思考回路を頭に入れておくと、全くわけのわからない問題が出ても、
「肢アが正しいとすれば、こういう事態になってしまうがそれは法的に見ておかしい。そんなルールを作るはずがない」
「肢イは確かに法的にはあり得そう。別のところで習った○○という制度と似ているからあってもおかしくない」といった感じで、食らいつくことができます。
こういう食らいつきができると、肢が複数残ってわからなかったときでも、鉛筆を転がすよりかは正解する確率を上げることができます。
【3】足腰とリーガルマインドを「効率よく」身に着けるには
以上のとおり、基礎力(足腰)とリーガルマインドを身に着けることで、経営法務が難化傾向を示しても突破できる可能性を高めることができます。
もちろん、これらを自ら身に着けていくことも可能です。しかしせっかくゴールデンウィークがあるのですから、そこで集中して身に着けてみませんか。
5月5日に、LEC池袋本校で経営法務「苦手意識は今日でさよなら道場」を実施します。この「道場」では、当日のリアル講義で、経営法務で頻出の「基礎的」分野と、それらの説明を通じて「リーガルマインドとはどういうものか」ということをお伝えます。
経営法務が苦手な方はもちろん、難化傾向になったらどうしようと不安に思っている方も対象です。ぜひゴールデンウィークに経営法務を盤石なものに仕上げてしまいましょう。
ここまでお読みいただきましてありがとうございました。一次試験も近づいてきています。一緒に最後まで頑張っていきましょう!

法律事務所勤務を経て、現在は外資系ファームのコンサル部門に所属。
コンサル部門に所属したのちに勉強を始め、2016年に中小企業診断士試験に合格。
中小企業診断士の情報を今すぐキャッチしよう