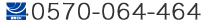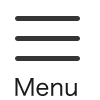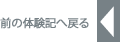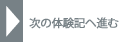「こう書け!」はよくできた奇跡の教材
会社員(40代男性)
| 主な受講講座 | 短答合格コース → 論文合格コース → 論文集中強化コース |
|---|---|
| 論文受験回数 | 2回 |
| 学習開始時期 | 2016年12月 |
不動産鑑定士を志した理由
何か資格を取りたいと思い色々と調べていくうちに、不動産鑑定士を知り、面白そうだと思ったからです。
合格までの軌跡
2016年12月から開始し、2019年10月の論文式試験合格に至るまでの私の不動産鑑定士試験の受験勉強は決して平坦なものではありませんでした。短答式試験を一度目不合格になり、さらに論文式試験も一度目は不合格になりました。しかし、それを乗り越え合格を手にした現在において私はこの試験から様々なことを学ぶことができました。
私は、人生を賭けて何か大きなことにチャレンジしたいという思いから、不動産鑑定士試験を受験することを決意しました。大変な試験であることは前もって知っていましたが、実際にやってみるとそれは想像を絶する過酷さで、特に基準の暗記が思うようにはかどらず、もう辞めてしまおうと思ったことは一度や二度ではありませんでした。
しかし、受験勉強は誰に強制されるわけではなくあくまで自分で決めたこと。だから結果がどうなろうと、最後までやりきろう、自分自身との勝負に決着をつけてやろう、という思いで乗り切りました。
本試験当日は体力、精神力共にプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも試験に臨みました。試験日3日目、最後の科目の鑑定理論・演習が終わったときはもはや満身創痍で、色々な感情が入り乱れどこからともなく涙が溢れてしまい、試験終了後しばらく立ち上がることができませんでした。
このときの感情はもはや言葉では説明できるものではありませんが、少なくとも、自分の限界というところまで自分を追い込み、そして自分自身との勝負に決着をつけた瞬間であったことは間違いありませんでした。
最終合格を果たした現在、過酷だった受験勉強期間を振り返ってみると、辛いながらも困難に立ち向かっていた日々や、毎日毎日、来る日も来る日もひたすら基準を暗記していた日々が実はとても輝いていて、充実感に満ちていたのだということに気が付きました。
不動産鑑定士試験とは私にとって、ライセンス資格を取得するという意味だけでなく、最後まで諦めないことなど人生にとって大切なものとは何かということを教えてくれた試験でありました。このような素晴らしい経験をさせてもらった不動産鑑定士試験に感謝をせざるを得ません。
そして、今後は、不動産鑑定の実務の世界で経験を積み、説明責任をしっかり果たせる不動産鑑定士になる。という新たな目標のために努力していきたいです。
もちろん、その過程においても困難や壁にぶつかり挫折感を味わうことに必ずなると思います。しかし諦めず最後まで粘り強くやりきれば必ず結果がついてくることを私は不動産鑑定士試験勉強において学びました。したがって私はこれから訪れる幾多の試練も乗り越え、必ず立派な不動産鑑定士になれることを信じています。
LEC講師の良かった点
豊岡講師は、答練や模試の採点がとても丁寧、細やかな指摘で、具体的にどこをどのように改善すればよいかをよく理解することができました。また、「論文直前ファイナル模試」(オプション講座)の解説講義において「最後まで諦めない」という熱いメッセージがとても心に響きました。ありがとうございました。
LECの教材・講義で役立ったもの
民法と会計学は、ほとんど「こう書け!」しかやっていません。他の科目についても、「こう書け!」の内容は試験に必要な論点が一通り網羅されているので、何回も回すと相当に力がつきます。 私は、「こう書け!」がなければ絶対に合格していなかったと思います。相当によくできた奇跡の教材と言っても過言ではありません。
経済学は、「必修論点総ざらい講座」において、より実践的な問題を扱うことになります。したがって、「合格基礎講座」等で学んだ内容を基礎にして、「必修論点総ざらいテキスト」を何回も解くことによって本試験で十分に対応できるだけの力がつくと思います。他の科目に関しては、それまでなんとなくあやふやだった知識が、しっかりと形になり定着させることができました。
論文対策で、学習法や工夫した点
学習法としては、全ての科目で「合格基礎講座」以外、ほとんど「合格基礎テキスト」は使用しなかったです。私は、テキストを熟読するという勉強法はあまりなじめず(いつも眠くなってしまう)、それよりは「こう書け!」などのように問題形式になっていて、答案構成を自分でやりながら進めるアウトプットしながらのインプットのほうが眠くならずに学習できました。基準・留意事項の暗記に関しては、特殊なことはしていません。私は、完全なる音読派で暗唱できるまでただひたすら音読したのみです。そして1日のノルマは決めてあり(約1週間から10日で1週する)、そのノルマは最優先事項で絶対に欠かさないようにしました。ただ、基準・留意事項の暗記は、初めは死ぬほどきついですが、ある一定の壁を越えてくると、途端に楽になるのがわかります。最後の時期はもう鼻歌まじりになっていました。
合格したときの率直な気持ち
2018年に不合格になってからの1年間は自分の限界を超えているのではないかというほど勉強しました。そして、もう今年落ちたらもう1年同じ勉強は自分にはできないとの思いがあったため、嬉しいという感情よりも、ほっとしたという安堵感の方が強かったです。
これから不動産鑑定士試験を受験される方へ
私は1年目に鑑定理論の点数が足りずに落ち、2年目は鑑定理論で点数を稼ぎ合格しました。不動産鑑定士試験とは「鑑定理論に始まり、鑑定理論に終わる試験である」と、2回の論文式試験を通してつくづく思い知らされました。さらに言えば、基準・留意事項の暗記が鑑定理論の生命線であり、不動産鑑定士試験の生命線であると確信しています。そして、この暗記は初めはつらいかもしれないですが、必ず壁を越えて楽になる時期が間違いなく来ます。そしてその壁を越えたならば合格というゴールはもうすぐそこにあるに違いありません。