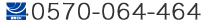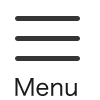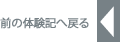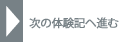LECの「こう書け!」のみで合格を勝ち取った
金融会社勤務(40代男性)
| 主な受講講座 | 論文合格コース → 論文徹底強化コース → 論文集中強化コース |
|---|---|
| 論文受験回数 | 3回 |
| 学習開始時期 | 2015年10月 |
不動産鑑定士を志した理由
今から25年前に完全リタイアしてから不動産鑑定士試験に挑戦し合格して開業した会社の大先輩の姿に接し、憧れたためです。
具体的な学習方法
不動産鑑定士試験への挑戦前に宅建士と簿記2級を受験して基礎知識を蓄えた後、2015年10月にLECの通信講座を申し込んで、仕事をしながらの本格的な試験対策を開始し、平日の通勤時間と帰宅後及び週末を勉強時間に充てました。
通勤中は基準暗記の時間と決めて、「モバイル鑑定評価基準」を常に持ち歩いて隙間時間を使って通算103回読み込みました。「モバイル鑑定評価基準」には、LECの答錬の模範解答で引用された基準の箇所に下線を引いて重点的に覚える部分を可視化した他、答錬の開設の要約を書き込んで独自の参考書を作り上げました。
自宅でしかできないDVDの視聴と答錬作成は、LECから送られてきたDVDは全て見る、答錬は全て提出するの2点を心掛けました。
論文対策としての暗記は「こう書け!」のみを使い、量重視で教養科目は通算36回、鑑定理論は通算51回読み込みました。暗記にあたっての科目別の工夫点は次の通りです。民法は、問題文と関連条文を見たら論点(問題・規範定立・理由)が思い浮かぶようにするために専用ノートを作りました。この際、「こう書け!」の解答は既出の論点が省略されていることがあるので、専用ノートには省略された論点についても漏らさず書くようにしました。経済は、記憶が曖昧な用語の定義や時事ネタとの関連などを「こう書け!」の余白に書き込んで解答を思い出しやすくする工夫をしました。会計学は、具体的な財務諸表(例えば「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」)の事例や、正確に記憶する必要がある定義を「こう書け!」の余白に補記して暗記に努めました。鑑定理論は専用ノートを作り、問題文の下に「こう書け!」に書かれている解答の流れの箇条書きを書いて論文構成の練習帳として使いました。また、川原講師オリジナルの語呂合わせも追記して暗記カード的な使い方もできるようなノート構成にしました。
答錬は、論文は解説冊子を読んだ後に解答例を3回紙に書き写して各科目固有の答案の書き方に慣れる、演習は解説冊子をチラ見しながら2回問題解きをして評価手法の適用に慣れることを重視した復習をしました。
このような工夫をして試験対策をしましたが、苦手意識が強かった民法と鑑定理論は「こう書け!」の問題と解答とのつながり、問題に対してどうして「こう書け!」の解答になるのか腑に落ちるようになったのは3回目の論文に向けた勉強を始めてからで、それまでは分からないイライラを我慢しながら回数を重ねる日々でした。いま振り返ると、暗記量が一定量を超えたことで腑に落ちるようになり始めたのだと感じます。そういった意味では、不動産鑑定士試験は「1に暗記、2に暗記、3、4がなくて5に理解」の試験なのだと思います。
私が工夫したことの一つでも、これから不動産鑑定士試験に挑戦なさる皆様のお役に立てば幸いです。
LEC講師の良かった点
森田講師は、「経済学での世の中の捉え方」という観点から理解を深めて行くことができ、これは結果として近道を歩んでの勉強ができたと感じます。
LECの教材・講義で役立ったもの
「こう書け!」シリーズです。この教材のみで合格を勝ち取りました。
論文対策で、学習法や工夫した点
暗記量を増やすために数をこなすこと、「こう書け!」シリーズを何回もまわすことです。
合格したときの率直な気持ち
明日からモバイル鑑定基準を持ち歩かなくて済む!良かった!
これから不動産鑑定士試験を受験される方へ
不動産鑑定士試験は、努力が必ず報われる試験だと思います。諦めず頑張ってください!