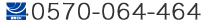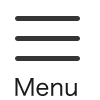早川先生には自分の弱点を分析した適確なご指導をいただきました。
方山 晋一 さん (60歳代)
| 受講講座 | 年金キーパー+中上級コース(通学) |
|---|---|
| 受験回数 | 4回 |
社労士受験を志した理由
自分の亡き父が会社員を退職すると同時に社労士の資格を取得して、自宅で社労士事務所を開業しました。身近で父の社労士としての仕事ぶりを見ていて、社労士の仕事に憧れを持ったのがきっかけです。
LECを選んだきっかけ
社会人になって3〜4年目の時ですから、かなり昔ですが、宅建の資格取得時にLECさんにお世話になったことと、社労士講座の受講を決めるにあたり、大手予備校をいくつか回りましたが、LECさんの説明が一番丁寧で、相談にも色々と乗って頂いたからです。
インプット時期の学習方法を教えてください
LEC中上級講座のカリキュラムはよくできていますので、基本的には、カリキュラムに沿って、各科目のテキスト予習とWeb講義視聴→生講義の受講→テキストの復習や理解しづらかった箇所のWeb講義再視聴→最後に確認テストや本試験答練を受けて間違った箇所の復習ということを繰り返しました。ただ、1〜2ヶ月もするとせっかく覚えた学習内容を忘れてしまうので、事前に計画を立て、各科目について繰り返しテキスト読みや過去問を解くことにより復習し、知識の定着化を目指しました。
実戦答練以降の学習方法を教えてください
実戦答練以降は、インプットも終わっていますので、早川先生のご指導もあって、積極的に他社の模試などを受けることによって、実戦力のアップを目指しました。自宅で市販の模試を解く時も、必ず各科目の解答目標時間を決めて解き、実績も計りました。また、模試で間違った箇所はテキストに戻ってしっかりと復習しました。判例講座や白書講座のテキストも繰り返し読み込みました。
スランプ克服法・苦しい時、どう乗り切りましたか?
2回目と3回目の受験で連続して、自分の凡ミスから、選択式などで基準点割れを起こし、あと1点というところで合格を逃したことです。社労士試験の難しさを思い知らされた感じでした。特に3回目の受験での失敗は、模試でも本試験でも択一式が55点前後取れていただけに、流石に心が折れそうになりました。立ち直るのに1ヶ月以上はかかりましたが、ここで挫けてなるものかと、あきらめずに頑張りました。絶対に合格してみせるという信念というか、精神力で乗り切りました。
仕事や学業、家事・育児との両立するための工夫
仕事との両立が一番難しかったですが、事前に計画を立て、朝や昼休みなどのすき間時間を有効に使って、毎日最低3時間は学習するようにしました。それでも計画通りいかない時は、土日に補強しました。
LECで受講して良かった点
良いカリキュラムと良い講師に恵まれたことです。早川先生には自分の弱点を分析していただいた上で、適確なご指導をしていただきました。本当にありがとうございました。
全日本社労士公開模試を受験して良かった点
自分の実力や時間配分の適正さなどを客観的に測ることができる手段として、大変有効でした。間違ったところをしっかり復習することにより、実戦力のアップに繋がったと思います。
2024年に受講した道場講座を教えてください
【早川講師】早川の年金法特訓道場
年金科目(国年、厚年)にかかる知識の体系的な整理や実戦力、得点力のアップに繋がったと考えており、受講して本当に良かったと思いました。おかげさまで、令和6年度の本試験では、厚年9点、国年10点を取ることができました。
フォロー制度の活用方法について
各科目の生講義(通学)を受講する前に、必ずテキストの予習とWeb講義を聴くようにしました。生講義受講後に理解が十分できていない箇所については、Web講義を繰り返し聴き復習することによって克服しました。難しい箇所や自分として理解しづらい箇所について、Web講義を繰り返し聴くことによって、理解することができました。
社労士資格をどう活かしていきたいですか?
私の場合、現在60歳を超え、セカンドキャリアの真っ最中です。今のところは、このまま現在の会社で65歳まで働き、その後は社労士として独立開業することを考えております。現在の会社に勤めている65歳までの間に、更に年金アドバイザー2級やFP2級の資格を取り、社労士としての開業後は、年金を中心に総合的なコンサル業務をできればと考えております。
これから受験される方へのメッセージ
これから社労士試験を受験する方へのアドバイスとして以下3点を挙げます。頑張ってください!一点目は、得点源となる得意科目を作るべきということです。私の場合は、早川先生のもとで学習し年金を得意科目にすることができました。早川先生は年金の仕組みや仕掛けからわかりやすく教えていただけるので、年金を得意科目にしたい方にはお奨めです。二点目は、受験2回目以降の方は早い時期、できれば10月頃から、判例や厚労白書を繰り返し読み込むべきということです。選択式対策として大変有効ですし直前期の5月頃からでは手遅れの感があります。三点目は、学習した重要ポイントなどはノートなどに整理して書いてみることが有効であるということです。講義では、読んだり聴いたりすることが多いですが、自分なりに科目横断的にポイントを整理して書いて覚えることは、記憶の早期定着化に繋がり大変有効です。