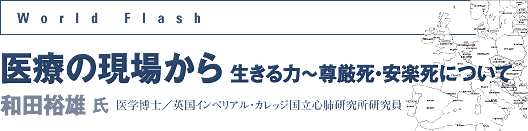|
|
|
|
医師の第一義的目標は「病気を治すこと」だと思っています。私もイギリスで「喘息と慢性閉塞性肺疾患の治療法の確立」を目指しています。しかし、治療方法がない病気はたくさんあります。病気の末期には、いろいろな症状が合併しますが、なかでも「麻痺」は患者に死への恐怖と絶望を与えます。
われわれ医師は「麻痺」だけは合併させないように全力を尽くします。 最近イギリスで話題になったケースですが、Diane Prettyという女性が運動神経疾患にかかり、四肢が麻痺し、呼吸は人工呼吸器で、コミュニケーションには音声合成機を使い、栄養、水分、排泄、すべて介助が必要な状態となってしまいました。この状態では自らの尊厳を保てないと考え、愛する夫の助けを借りての「尊厳死」を希望して裁判所に訴え出ます。裁判所は尊厳死による自殺は認めますが、自殺幇助は犯罪であるという立場で事実上彼女の願いは聞き入れられませんでした。書くこともできない彼女は音声合成機を通 して「法は私から全ての権利を奪ってしまった」と嘆くのみでした。医学からも司法からも彼女は「満足」を得ることはできず、ただ耐えるだけの余生が求められたのです。 ヨーロッパ人権法廷がMs. Prettyに下した「生命、非人間的な医療からの自由、そしてプライバシーの尊重等の権利は守られている」という判断の論点は尊厳死・安楽死の是非ではありません。運動神経疾患の患者団体も「残酷な病気であることが強調された事件だ」としながらも、Ms. Prettyを支持も反対もしないという立場でした。如何に難しい問題であるかが解ります。 私の研究所にはヨーロッパ各地から留学生が来ていますが、Ms. Prettyの事件は有名で皆知っていました。私が意見を求めると、「救急医療の教育は受けたが、この手の末期医療や安楽死の教育は受けていない。確かに難しい問題だ」。「ヒロオは、医学博士(Doctor of Philosophy)だから哲学(Philosophy)の難しい話をして困る」。「こういう問題はサイエンスをベースとした医療で解決するよう教育されている。キリスト教などの宗教が出てくることは絶対にない」。 「自分の場合なら苦しいのは嫌だから自殺する方法を考えるかもしれない。でも患者にそんなことは絶対しない」。と直接的な解決法は解らなくとも、安楽死や自殺幇助は医師の仕事ではないという意見でした。英国医学協会(British Medical Association)も「自分の病室に入ってくる医師が治療者の白衣を着ているか、死刑執行人の黒いフードを冠っているか、なんて決して考えたくない。医師と患者の人間関係は重要でもろいものだから…」(Alexander Capron)という言葉を引用して「自殺幇助」と「安楽死」を明確に否定しています。 イギリスでは、1990年代から安楽死が問題になり医師も一般の人も積極的に議論に参加しています。ちょうどMs.Prettyが提訴した頃、ある医師が医学倫理の観点から「自殺幇助と安楽死を容認すべきだ」と雑誌に意見を述べたところ、大きな反響を呼びました。賛否様々でしたが目立った意見は「そういう医師にはかかりたくない」、「自殺幇助と安楽死は医師の仕事ではない」というものでした。 私もこの意見に賛成します。患者から治療に関して意見を求められた場合は、私は病気と闘うことを勧めています。日本であれば、一人ひとりの患者こそが日本をこれだけ豊かにし、日本の医療を発展させ、現在の状況を作り出した原動力ですからその最良の成果 を享受すべきだと思うからです。 「さあ、これから、人生観の勝負だ!」。 これは私が研修医になったときの先輩の言葉です。 私はその時、脳梗塞による広範な脳障害でMs. Prettyと同じ様に四肢麻痺で全介助になった女性を担当していました。この女性は失語症も合併していましたが、私が点滴、経管栄養補給などを行おうとすると、涙を流したり顔をしかめたりと抵抗し、退院希望を表明しました。何度も在宅介護のプランを立てましたが、夫は仕事と介護が両立しないことと病気への不安を訴えました。私も自宅への退院は困難と考え、ケア中心のリハビリ病院への転院を検討していました。ところが、私の指導医は「往診もするから」とかなり強引に退院させました。同僚の医師もその強引さにビックリして眉をひそめていました。が、1ヵ月ほどして夫が来院し、仕事と介護の両立が可能であったこと、患者の女性が退院をとても喜び食欲も回復したこと、そして、息子が介護を手伝うようになったこと、夕食は家族全員揃って食べるのだ、と嬉しそうに話してくれました。 もし、私が最初の計画通りその女性をリハビリ病院へ転院させていたら、このような家族の悦びを奪うことになっていたと思います。自分の人生観の敗北を知り、医者の人生観によっては全く異なる結果 になり得ることを学びました。 患者は、自動車のように運転手の思いのままに操れる機械ではなく意志ある人間です。医者の人生観だけで左右されるわけはなく、自分の人生観を持っています。さらに家族の人生観にも大きく影響されます。 私の恩師が入院して手術をすることになり、お見舞いに行きました。病室では奥様がずっと看病なさっていました。「何かお困りのことはないですか」と尋ねますと、本を読むと隣の患者が音を出してテレビを見たり、挨拶をしても無視したり意地悪だと言います。確かに複数の患者が同室の場合、家族が見舞いにこない患者は入院が長引くと寂しく思い、考えも行動も荒んできます。ちなみに私の恩師は個室に移りました。 また、ある老人病院は農村地帯にあり、夕方、家族が仕事の帰りに見舞いに来ます。特に医師・看護師に会って病気や状態について尋ねるわけでもなく「ちょっと買い物ついでに立ち寄った」という感じで来院するのです。その時のおとしよりの笑顔を見ているとこちらの心も和んできます。もちろん病棟管理の一環として、家族のよく来る患者とあまり来ない患者が同じ部屋にならないような工夫もしていましたし、あまり来ない患者の家族にはお見舞いに来るよう指導もしていました。 家族の支えがあれば患者の人生も変わってくるのではないでしょうか。私は医師として「死にたい」という言葉を疑うことから始めます。それは状況が変われば考え方もきっと変わると信じているからです。 Ms. Prettyは二児の母親で夫も健在で家族に恵まれているのですから、家族に人生の生き甲斐を見出すことができれば死にたいなどと悲しまなくて済んだかもしれません。実際、同じ病気でも彼女と異なる考え方の患者はたくさんいます。私のスペイン人の同僚は、「呼吸器科医として運動神経疾患患者の人工呼吸管理を行ってきたが、『娘の成長が楽しみなので、動けなくてつらいけれども死にたくない』という患者がいて一番長生きしている」と話してくれました。 私が担当した運動神経疾患で肺炎を併発し入院してきた青年はベッドの上で寝たきりでしたが、話すことができ、両手も自由でしたので、放送大学を受講し、イラストを描く勉強をしていました。個展を開いたり、地元のラジオ番組に出演したりと、活躍している話を私にしてくれました。その陰では彼の才能を、母親がしっかりと支えていたのです。 家族や仕事に人生を見つけ出せれば、悲しい選択を考えなくても良いのです。 Cambridge大学のStephen Hawking教授は21歳でMs. Prettyと同じ運動神経疾患を発症しましたが、その後、「A brief history of the time」(『ホーキング、宇宙を語る』)を書き、40年間社会で活躍し、最近60歳の誕生日を迎えました。その誕生日のインタビューに音声合成機を使用して次のように答えていました。 「運動神経疾患でも、私には素敵な家族もいる。仕事も上手くいっている。娘のJaneのおかげだ。なにも希望を捨てる必要はない」。 |
PROFILE 1968年生。1993年東大医学部卒。英国インペリアル・カレッジ国立心肺研究所に留学中。医学博士。日本内科学会専門医。 |